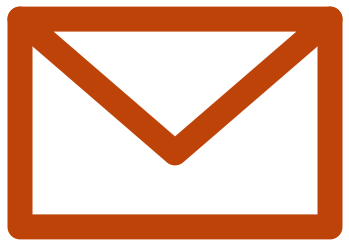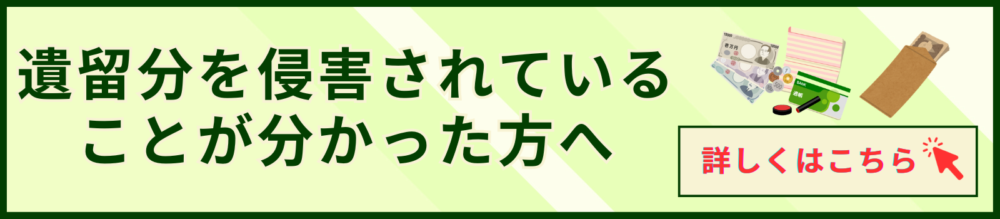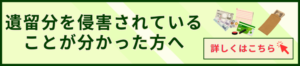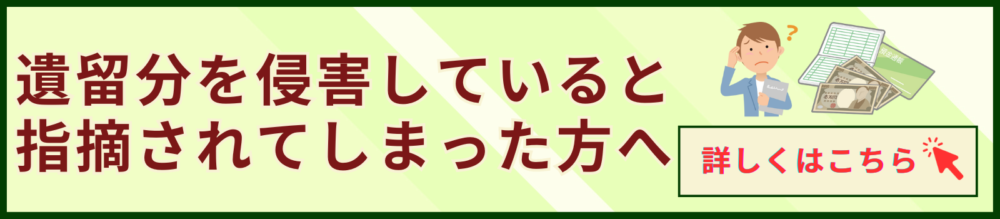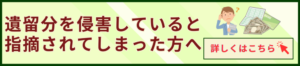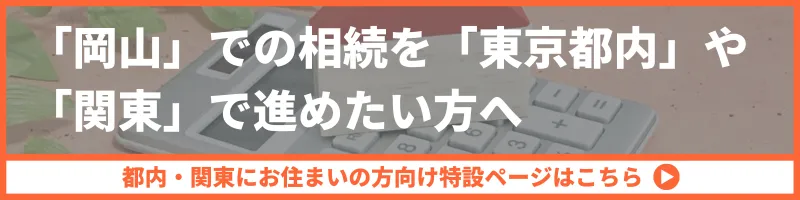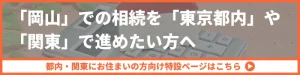訴訟手続


相続トラブルを解決するためには訴訟手続きが必要な場合もあります。また、遺言の有効性や偽造の問題に直面した場合、遺言無効確認の訴訟を提起することがあります。さらに、財産目録の作成も重要です。この記事では岡山の弁護士が訴訟手続きと財産目録作成法について解説し、円滑な相続解決のヒントをご提供します。岡山で相続トラブルを未然に防ぎたい方、訴訟になりそうな方は弁護士にご相談ください。


目次
訴訟手続きが行われるケース
相続関係において,裁判所の訴訟手続きを利用する場合として次のような場合があります。
遺言の有効無効に関する紛争
被相続人(亡くなった方)の遺言があるものの,その筆跡がおよそ被相続人のものであるとは言えず,遺言が偽造されたものである場合や,一方に有利な遺言書が見つかりトラブルが生じた場合,無効であると主張する遺言無効確認訴訟などがあります。
遺言書が偽造された場合
筆跡鑑定が実施された結果,遺言者本人の筆跡とは異なることが明らかとなり,その内容も特定の相続人にとって著しく有利なものである場合には,遺言無効確認訴訟を提起することになります。同訴訟において,何者かによって遺言が偽造されたことを主張し,遺言の無効を争うことになります。
仮に,特定の相続人が遺言書を偽造したことが証明された場合には,遺言が無効になるだけでなく,遺言書を偽造した相続人は欠格事由(民法891条5号)に該当し,相続権をはく奪されることになります。
その結果として,当該相続人は,法定相続分すら取得することができなくなります。
さらに,私文書偽造・変造罪(刑法159条),偽造・変造私文書行使罪(同161条)の要件に該当する場合には,偽造者を刑事告訴することもできます。
遺言者に遺言能力がない場合
また,相続人の一方に有利な内容の遺言書(自筆遺言証書)が見つかった場合に,遺言者が当該遺言を作成した時期の健康状態などから合理的に判断して,およそ遺言者が当該内容の遺言を作成することが困難であるといえるときにも,遺言の有効性を争うことができます。
具体例としては,確かに本人の筆跡ではあるものの,遺言作成当時,遺言者に認知症であり,自らの意思に基づいて当該内容の遺言を作成するだけの認知能力が十分に備わっているとは認めがたく,遺言者が内容を理解しないまま何者かに指示されるままに遺言書を作成したようなケースです。
遺言書が遺言無効確認の訴えにより無効となると,相続人間で相続財産の分配方法が決められていない状態になります。
したがって,その場合には,改めて相続人全員で遺産分割協議を行うこととなります。
もっとも,遺言が無効であると判断されるためには,証拠を提出して立証しなければならず,その証明は多くの場合,容易ではありません。
また,厳格な要式によって作成された公正証書遺言の場合には,遺言が無効と判断されるためのハードルはさらに高くなります。
遺言の無効が認められない場合には,遺留分を有する相続人は,遺留分侵害額請求権を行使して,自己の取り分を確保していくことになります。
ただ,遺留分侵害額請求権には期間制限があり,相続の開始から1年以内に行使の意思表示をする必要があります。
このような期間制限が設けられていることから,一般的には,遺言が無効と判断される事態に備えて,遺言無効確認訴訟の提起と並行して,遺留侵害額請求権を行使することになります。
相続前の金銭の使い込み
相続人の中に,生前に被相続人(亡くなった方)の財産を無断で使い込んだ者がいる場合,その相続人に対して提起する不当利得返還請求訴訟があります。
上記紛争については,訴訟になれば1年以上かかるケースも多々あります。可能であれば,早い段階の交渉により解決できれば早期解決することができ精神的な負担も軽くてすむといえます。
当事者同士ではなかなか話し合いができない場合でも弁護士に依頼することで,訴訟を提起せずに交渉で解決できることが多くあります。
遺産の範囲の確認
被相続人(亡くなった方)の預金であるはずが,預金の名義が相続人の1人の名義になっていて,その預金自体が遺産に属するのか否か争いがある場合に,相続人の一人から提起する訴訟として,遺産等確認訴訟などがあります。
遺留分侵害額請求
遺留分侵害額請求の交渉がまとまらない場合においては,その請求権に基づいて財産の移転を求める訴訟などがあります。
遺産分割トラブルは訴訟ではなく審判や調停での解決になります
まずは協議、その後は調停・審判へと進みます
遺産分割は本来、裁判所での解決を図る前に相続人同士の協議で合意形成を目指します。
最初に行うべきは相続人全員での交渉ですが、交渉が不成立の場合は家庭裁判所での「調停」を通して解決を目指します。調停でも決着がつかない場合には、自動的に「審判」に移行して裁判所の裁定によって解決を図るのが通常の流れです。
訴訟との違い
審判は、対立する当事者間の紛争を解決するという構図が訴訟に似ています。ただし、審判では正式な手続きの形式を守りながらも、家庭内の実情に合わせた柔軟な審理と判断が重視されます。
また、訴訟では当事者が請求した事柄のみが審理対象になりますが、審判の場合は処分権主義や弁論主義が採用されておらず、審判では請求されていない事柄についても裁判所が判断を加えることが可能です。
さらに、審判に対しては控訴が認められず、即時抗告のみとなります。
遺産分割は調停段階で解決することが重要です
調停が不成立に終わった場合、遺産分割は家庭裁判所での審判や訴訟に移行します。
しかし、審判や訴訟では裁判官が法律に基づいて妥当と判断する内容での決定を下すため、相続人各自の希望が反映されないケースもあります。調停で合意を図ることが、お互いに納得した遺産分割を行うための重要なポイントです。
相続トラブルを弁護士に相談するメリット
主張を法的に組み立て、有利な解決をサポートできます
相続問題において、遺産の分配方法や権利関係について、各相続人が異なる主張をして対立することが多々あります。
こうした場合、感情に流されず、法的な根拠を持って交渉に臨むことが重要です。弁護士は相続法や財産分与の複雑なルールに精通しており、依頼者の利益を最大限に守るため、根拠ある主張を組み立てていきます。
たとえば、特定の相続人に対する贈与が「特別受益」として認められるかどうかなど、相続分を決定する上で重要な点についても適切にアドバイスが可能です。法的視点から交渉に臨むことで、ご相談者様にとって有利な条件で解決が期待できます。
調停・審判への同席や代理出席が可能です
相続問題が家庭裁判所での調停や審判に進んだ場合、平日の日中に裁判所へ出向く必要があります。
しかし、仕事や家庭の都合で出席が難しい方も少なくありません。こうした場合、弁護士に代理出席を依頼することで、ご相談者様の代わりに調停や審判の場での対応が可能です。弁護士はその場で依頼者の権利を主張し、相続分の確保や遺産分割の公平性を求めて交渉を進めます。
他の相続人との間に入ることができます
相続問題では、長年の家族関係や感情が絡み合い、冷静な話し合いが難しくなることがよくあります。
たとえば、些細な誤解や過去の家族間のいざこざが原因で、話し合いが感情的になってしまうこともあります。このような場合に弁護士が介入することで、相続人同士が直接的な対立を避け、客観的な視点で問題解決に向き合うことが可能です。弁護士が第三者として間に立ち、法的な観点からサポートすることで、スムーズな合意形成が期待できます。
西村綜合法律事務所の弁護士費用
| 初回相談料 |
無料 30分〜1時間程度を目安としておりますが、ご状況に応じて最後までお話を伺います |
当事務所は岡山県に根ざした法律事務所として、地域の皆様が少しでもストレス・相続争いから解放されるよう、まずはご相談のきっかけとしていただくために初回相談を無料とさせていただいております。ご相談のみでお悩みが解消に向かうこともありますし、実際にご依頼いただかなかった場合でも費用がかかることはありません。
実際にご相談いただくことで想定以上の金額が戻ってくる場合も少なくありませんし、訴訟を起こさずとも弁護士が交渉に入るだけで相手の態度が変わってスピード解決に至ることも多々あります。
現在のご状況を正しく把握するためにも、まずはお気軽に無料相談をご利用ください。
着手金
交渉 27万5,000円〜
調停 38万5,000円〜
審判・訴訟 49万5,000円〜
報酬金
27万5,000円+経済的利益の11%
※上記を原則としながらも、事案によって増減させていただきます。
当事務所にご依頼いただいたことで
遺留分侵害額請求にて金融資産として約5,500万円を取り戻したケースや、
遺産の使い込みを明らかにし約2,500万円を取り戻したケースなどもございます。