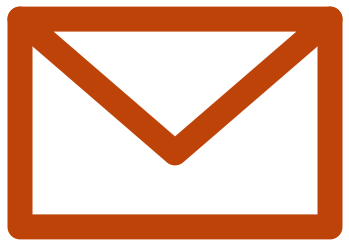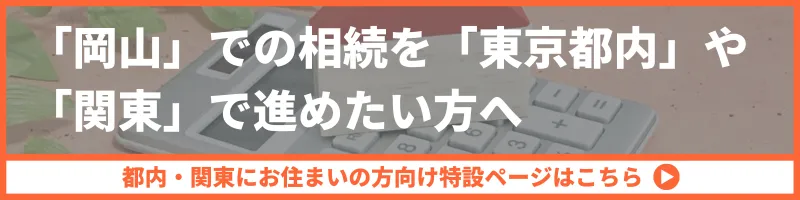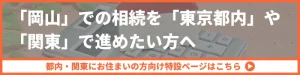相続人調査・相続財産調査


- ・自分以外の相続人が、預金やその他財産について教えてくれない
- ・自身でもで調べてみたが、全ての情報が得られたか判断できない
- ・連絡をほとんど取っていなかった親族から相続することになったが,借金が多そうで不安だ
- ・平日は忙しく、手続きの時間がとれない
- ・自分で戸籍収集や預金照会を試みたがが、手間がかかり複雑で行き詰まった
- ・他の相続人が遺言隠しをしている可能性がある
遺産分割を行う前に、上記のような不安をお持ちではないでしょうか。このような場合は相続調査の必要性が高いと言えるでしょう。相続人が誰なのか?相続財産はどんなものなのか?これらを正しく把握しなければ、家族の関係性に亀裂を産んでしまうかもしれません。家族・親族の絆を守るためにもまずは相続調査のご利用をご検討ください。


目次
相続人調査・相続財産調査について
まずは、相続人調査・相続財産調査について、それぞれ個別に詳しく見ていきましょう。
相続人調査
相続人調査は、相続人を確定させるために行います。
冒頭でも触れましたが、親族の方が把握していない相続人がいる可能性は十分にあります。
それを確認するためには、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本(除籍謄本、改正原戸籍等)をすべて取り寄せる必要があるのです。中には戸籍を転々としている方もいらっしゃるため、すべてを取り寄せるには複数の市区町村役場に申請しなければならない場合もあります。どうしても手間と時間がかかってしまう作業なため、相続人調査への着手は急ぎましょう。
また、古い戸籍謄本は、まだ手書きで作成されていたことから、記載されている文字の判別が困難なこともあります。あるいは、戦争などで戸籍が消失していて取得そのものが不可能といったケースもあり、その都度必要な対策を取らねばなりません。
どうしても戸籍謄本の取得が難しいと感じた際は、弁護士への相談をお勧めいたします。弁護士であれば、代わりにすべての戸籍謄本を取得した上、相続人を確定することができます。
相続財産調査
相続人の確定と相続財産調査は、並行して行うのが理想です。というのも、相続には主なところで、相続放棄は3か月、相続税申告は10か月といった期限があるためです。
相続財産調査は、一般的に被相続人と同居の相続人がいれば、ある程度把握している場合が多いですが、そうでない場合は調査に時間がかかることがあります。また、同居の相続人がいたとしても、他の相続人に対して相続財産を素直に公開しないこともあります。
こうした相続人同士のトラブルもあり、調査が円滑に進まないケースは現実にめずらしいことではないのです。さらに、相続は預貯金や不動産といったプラスの財産だけでなく、借金や保証債務といったマイナスの財産も対象になります。これらをすべて把握した上で、相続するかを3か月以内に判断しなければならない点も財産調査の難しいところです。
以下では、少しでも財産調査をスムーズに進めるための予備知識として、主要な財産の調査方法について簡単にご説明していきます。
現金については、被相続人の自宅を捜索するのが一般的です。タンス預金といって家庭内に現金を保管している方も多いため、自宅内をくまなく探してみましょう。
預貯金については、通帳やキャッシュカードはもちろん、最後の住所地や縁の深い地域の近辺にある金融機関を問い合わせてみるのも効果的です。
被相続人が不動産を保有している場合、自宅に権利書が保管されている可能性が強いです。
また、不動産には固定資産税がかかってくるため、年に1度、納税通知書が送られてきます。納税通知書が見つからない場合は、最後の住所地や縁の深い地域の役所にて、固定資産課税台帳(名寄帳)の写しを閲覧してみるという方法もあります。
負債(借金)については、カード会社からの支払い請求書などから調査するのが一般的です。
もし、請求書などが見つからなかった場合であっても、返済が1か月も滞ればカード会社などから連絡が来ますので、郵便物については注意深く確認するようにしましょう。
また、税金などの未払いについては、市区町村役場に問い合わせてみましょう。
生命保険の契約がある場合、自宅内に保険証書(保険証券)が保管されているはずです。
もし見当たらない場合は、届いた郵便物などから、被相続人との契約がありそうな保険会社に問い合わせをしてみるのが良いでしょう。もし契約があった場合は、保険証書(保険証券)の再発行といった手続きを行う必要が出てきます。
抵当権・借地権・賃借権については、契約書を探してみるか、見当たらなければ法務局にて登記事項証明書(登記簿謄本)の交付請求をしましょう。念のために、被相続人が保有していた不動産については、すべて登記事項証明書の内容を確認するようにしてください。
相続人調査・相続財産調査が必要なケースって?
相続人調査をすべき状況の例
相続人が誰かわからない(確定していない)
被相続人の戸籍をさかのぼってみたものの、誰が法定相続人に該当するのか分からないというケースは少なくありません。
特に、再婚歴がある場合、婚外子がいる可能性がある場合には、戸籍を丁寧にたどる必要があります。たとえば、前妻との間に子どもがいる場合、その子どもも相続人となるため、遺産分割を進める前に必ず調査しなければなりません。
戸籍謄本の取得や関係図作成を任せたい
戸籍は1通だけで済むものではなく、出生から死亡までをカバーするには複数の市区町村に申請しなければならないことがほとんどです。
また、古い戸籍は手書きで判読が難しく、理解しづらい表記もあります。これを読み解いて相続関係図を作成するのは、一般の方にはハードルが高い作業です。「手続きが煩雑すぎて進まない」という方には、弁護士への依頼が強く推奨されます。
音信不通・行方不明の相続人がいる
兄弟やいとこなど、長年連絡を取っていない相続人がいる場合、相続手続きがスムーズに進まないおそれがあります。
中には所在が不明で、生死さえ確認できないようなケースもあります。このような場合には、不在者財産管理人の選任や失踪宣告の申立てといった法的手続きが必要になることもあるため、専門家のサポートが不可欠です。
相続財産調査をすべき状況の例
相続放棄をするか否かの期限(3ヶ月)に間に合いそうにない
相続放棄は、被相続人の死亡及び自分が相続人であることを知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所へ申述しなければなりません。
この短期間で、プラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産まで把握しきるのは困難です。たとえば、預貯金があると安心していたら、実は多額の借金が後から判明することも。判断を誤らないためにも、早い段階で財産調査に着手することが大切です。
不動産や株式など多岐に渡るので正確な調査が難しい
相続財産が多岐にわたる場合、たとえば複数の不動産、複数の証券会社に分散した株式などがある場合、個人でそのすべてを調査するのは現実的に非常に大変です。
不動産であれば、名寄帳や登記簿謄本を取得しなければなりませんし、株式については各証券会社に照会が必要です。漏れのない調査を行うには、やはり専門的な知識と経験が求められます。
役所や銀行での手続きを平日に進められない
平日は仕事で動けず、役所や銀行に出向く時間が確保できないという方も多くいらっしゃいます。
しかし、相続手続きには期限があるものも多く、放置すると大きな不利益につながります。弁護士に依頼すれば、依頼者の代理として戸籍収集や金融機関への照会などを進めることができるため、安心して日常生活を送ることができます。
相続人調査・相続財産調査が不十分だとどうなる?
調査漏れのリスク(1)あとから他の相続人が判明するリスク
一見、相続人は全員把握していると思っていても、後から相続人が判明するというケースは意外と多くあります。
たとえば、被相続人に認知した子どもがいた場合などが典型です。こうした相続人が後から判明した場合、すでに行われた遺産分割協議が無効となるおそれもあります。時間と労力をかけた協議が水の泡になるのを避けるためにも、最初の段階で確実な調査が必要です。
調査漏れのリスク(2)遺産隠しや使い込み等を見抜けない
被相続人と同居していた相続人が、通帳や現金を隠していたり、遺産の一部を勝手に処分していたりするケースも見受けられます。
たとえば、死亡直前に大きな現金の引き出しがある場合、知らぬ間に不動産が売却されていたというような場合、しっかりと調査をしなければ他の相続人は気づくことができません。相続トラブルを未然に防ぐためにも、調査の徹底が重要です。
調査漏れのリスク(3)相続放棄の判断を誤ってしまう
プラスの財産ばかりを把握していたために、安心して相続を承認したところ、後になって多額の借金が発覚したという事例は決して珍しくありません。
相続放棄の期限である3ヶ月を過ぎてしまえば、原則として放棄はできなくなってしまいます。調査を怠ったことで、本来避けられたはずの債務を背負うことになるリスクがあるのです。
調査漏れのリスク(4)遺産分割協議のやり直しリスク
相続人や財産の把握が不完全なまま遺産分割協議をしてしまうと、後から新たな相続人や財産が見つかった際に、協議をやり直さなければなりません。
やり直しには時間と費用がかかりますし、関係者間の信頼関係にも悪影響を及ぼします。場合によっては、再協議が成立せず、家庭裁判所での調停や審判に発展することもあるため、最初から正確な調査を行うことが望ましいです。
相続調査を当事務所にご依頼いただくメリット


当事務所では、ご依頼者様のご事情に合わせて、相続人調査と相続財産調査を分けて承ることができます。これにより、費用の削減につながるメリットがあります。また、相続人・財産ともに全くわからないという方や、煩雑な手続きや他の相続人との連絡を手放したいという方は”相続人調査・財産調査お任せプラン”が大変おすすめです。
また、相続人調査の場合は「相続関係図」、相続財産調査の場合は「遺産目録」といったように、関係各所にそのまま提出できる形式にて書類作成いたしますのでご安心ください。
また、上記はあくまでも基本的なケースであり、個々の複雑な事情に合わせて個別に金額をご提案することも可能となっています。どうかお気軽にお問い合わせください。
調査後に発生する各種手続きへの対応
当事務所では、単に調査をして終了ではなく、調査後に発生する各種手続きについてもすべて対応可能です。
たとえば、相続財産調査をしたところ債務超過が判明したため「相続放棄」がしたい、相続人が確定したため法務局にて「法定相続情報制度」を利用したいなど、ご要望に応じた対応をさせていただきます。また、相続人調査によって誰も把握していない相続人が判明した場合などは、ご依頼者様の代理人として間に入っての交渉も可能です。
相続財産の分配に関するご提案
遺産・相続人調査が終了した後、相続人が複数いる場合は遺産分割協議を行うことになります。
その際は、相続財産の分配に関するご提案をさせていただくことも可能です。
また、相続人同士のトラブルなどによって、遺産分割協議が難航している場合は、当事務所が介入し、スムーズな話し合いが実現できるようお手伝いをさせていただきます。
交渉段階での解決に向けたサポート
遺産分割協議というのは、相続人全員の合意を得るのが難しい場合、最終的には調停・審判といった、裁判所の手続きを利用しなければなりません。しかし、裁判所での手続きは多大な時間と労力がかかってしまうことから、負担がどうしても大きくなってしまいます。
そこで、当事務所では交渉段階で解決することを第一とし、調停・審判を利用することなく円満な合意ができるよう、全力でサポートさせていただいております。
相続人・相続調査の費用
では次に、相続人・相続調査にかかる費用についても見ていきましょう。
すべて個人で行う場合、いずれの書類も1通あたり数百円程度で取り寄せることが可能です。よって、かかる費用は実費分となり、一般的には数千円程度で済むこともあり得ます。しかし、すべて個人で行うには多大な労力と時間を消費することになる他、調査漏れがあった場合は遺産分割協議のやり直しや家族関係への亀裂へと繋がりかねません。
ここでは、弁護士といった法律の専門家に依頼した場合の費用相場についても見てみましょう。
一般的な相場費用
弁護士等に依頼した場合の一般的な相場としては、10~30万円程度とされています。また、それとは別に実費分の費用がかかることになります。
当事務所へのご依頼費用
当事務所の場合、相続人調査と相続財産調査を個別に承ることも可能ですが、合わせてご依頼いただける”相続人調査・財産調査お任せプランが”便利です。
相続人調査・相続財産調査お任せプラン 220,000円
220,000円
遺言がない場合において、遺産分割協議の前提となる相続人調査・相続財産調査を行います。
- 主なサービス内容
- (1)相続人調査および確認
※相続人が5名以上存在することが分かった場合は6人目以降につき1人あたり11,000円 を追加 料金として頂戴いたします。 - (2) 相続関係説明図作成
- (3) 相続財産調査 不動産・預貯金など
- ※名寄帳は2つまで。金融機関は5つまで。それ以上の場合は1社あたり16,500円となります。
※金融機関が県外になる場合は別途お見積りとなります。 - (4)皆様のご状況に応じて最適なアドバイス・ご提案をいたします。
故人の戸籍収集
どんな親族がいるのか調査するため、戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍を取り寄せます。
相続人が生きているかの確認
戸籍の収集で判明した相続人が、現在生きているかどうかを調査します。
代襲相続人の調査
相続人が亡くなっている場合、相続の権利が子や孫に引き継がれるのかどうか調査します。
面識がないもしくは遠方に住んでいる相続人の調査
日常的に関わりのない相続人がいないか調査いたします。
被相続人の意思能力の調査
遺言などによって事前に準備されていた場合、当時の被相続人に意思能力があったと言えるか調査します。
保有していた不動産の評価
保有していた不動産の評価額を調査します。(状況により不動産会社などに依頼する場合は別途費用がかかります)
不動産登記・評価情報の調査
被相続人が保有していた不動産の登記情報の調査と、実施済みである不動産評価の情報を調査します。
預貯金の調査
故人の保有していた預貯金について、過去の取引内容をさかのぼって(原則:過去3年~10年)調査します。
銀行・信金等への残高照会
手間と時間がかかるケースが多い「預貯金の残高照会」を当事務所で行います。
上場株式・投資信託の照会
被相続人の上場株式や投資信託等の運用があったかどうか調査を実施し、残高や運用損益に関する情報を集めます
証券会社へ取引高の照会
証券会社への取引高の照会を行います。
保険の契約があったかの調査(故人が受取人になっている保険)
すでに亡くなった人がが受取人に指定されている保険があるのかどうか調査します。
会社株式などの評価額の調査(被相続人が経営者だった場合)
税理士と連携し、保有株式の評価額を算定します。(別途税理士費用が発生いたします)
相続財産目録の作成
上記のような調査内容を踏まえて、遺産分割協議で利用可能な相続財産目録を作成します。
遺言のあったか否かの調査
自筆証書遺言もしくは公正証書遺言が残されていないか調査します。
西村綜合法律事務所では岡山の皆様向けに初回無料相談(オンライン可)を実施中ですのでお気軽にお話をお聞かせください。