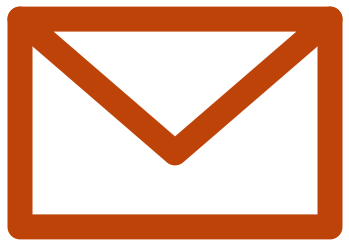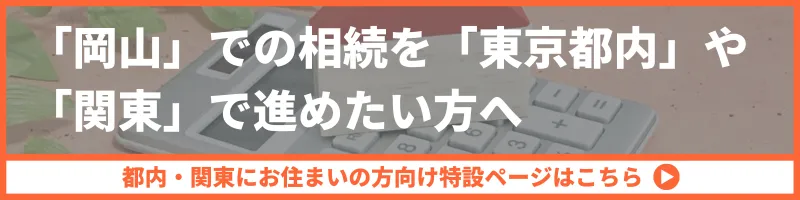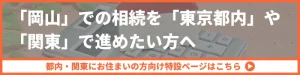特別受益や寄与分 – 相続で不平等になるケース


特別受益や寄与分という言葉自体は、一度は耳にしたことがあるかもしれません。また、遺産分割の協議や調停においても、他の相続人に特別受益がある、自分には寄与分がある、との主張がなされることは多くあります。
しかしながら、その意味を正確に理解している人は少なく、法的には特別受益や寄与分として認められないものを延々と調停で主張される方が多く見受けられます。これにより、遺産分割問題がいたずらに長期化し、あるいは長期化させることになり、相続人全員に不利益をもたらしてしまいます。こうした事態を防ぐためにも、特別受益・寄与分について確かな理解をしておくことが重要です。
そこで本稿では、特別受益や寄与分とは一体どういうものなのか、特別受益や寄与分が認められるのとそうでないのとでは、どのような違いが生じるのかを解説したいと思います。
「持戻し(もちもどし)」は、特定の相続人が自身が相続した財産を、他の相続人に対して返還することを指します。
通常、相続分の財産を受け取った相続人が、その一部または全部を他の相続人に返す際に使われる言葉です。これにより、相続分の均等分割や遺産分割協議を円滑に進めることができます。


目次
特別受益とは
被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた場合、その受けた利益を特別受益といいます(民法903条)。簡単にいうと、被相続人から、特定の相続人が生前に受けた特別な利益のことを言います。
このうち、特に問題となるのが「生計の資本としての贈与」という部分です。生計の資本としての贈与とは、一般的には「広く、生計の基礎として有用な財産上の給付をいう」などと説明されますが、これだけでははっきりと何が「生計の資本としての贈与」にあたるか明確ではないように思います。
そのため、相続人の一人が生前被相続人から受けたある受益について、それが特別受益にあたるかどうか実務家の間でも見解が分かれることもしばしばあります。
特別受益が問題になるケース:財産の前渡し
特別受益について問題になりやすい事として「財産の前渡し」が挙げられます。これは、被相続人が死亡する前に、一部の相続人に遺産としての財産を渡してしまうケースを指します。
このような事例では、一見して「贈与」としての性質が強いように思えますが、実際にはこの前渡しされた財産が、後に「特別受益」として考慮される可能性が高まります。これは、前渡しを受けた相続人が他の共同相続人と比較して過度に利益を得ている場合、特にそのリスクが高くなります。
例として、父が死亡する前に、 長男に家を譲渡したとしましょう。この家の市場価値が高額である場合、長男は明らかに他の相続人と比較して不当な利益を得ている可能性があります。このようなケースでは、家の譲渡が「生計の資本としての贈与」として考慮され、特別受益とみなされる可能性が高まります。
このような問題に対応するためには、被相続人が生前に財産の前渡しを行う際に、適切な文書でその意向を明確にすることが重要です。
特別受益の対象となるものは?
あまり答えにならない答えで恐縮ですが、遺贈又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けたものは、すべて特別受益の対象となります。受益した時期は問われません。
ただ、これだけでは特別受益について全く理解することができませんので、以下ではよく問題となるいくつかのケースについて解説したいと思います。
婚姻・養子縁組のための贈与
婚姻・養子縁組の際の持参金・支度金が特別受益に含まれることについては争いがありません。
もっとも、結納金や挙式費用を親が支出した場合については、親(被相続人)が支出するこれらの費用は、婚姻・縁組当事者(推定相続人)に対する親からの贈与というよりは、結納の相手方の親に対する贈与、挙式に関して親がみずからのために費やした契約費用であると考えられます。
大学の学費・入学金
大学の学費・入学金については、将来の生活の基礎となることは明らかであるから、親の資力にかかわらず、生計の資本としての贈与に該当するとの見解もあります。
しかし、資産状況や子どもらに与える教育レベルなどは各家庭で様々ですから、大学の学費や入学金であるからといってこれを一律に生計の資本としての贈与と考えるのは実態にそぐわないといえます。
したがって、大学の学費・入学金については、それが親の子に対する扶養の範囲内といえるかをしっかりと検討した上で判断すべきであり、こうした見解をとったと思われる審判例も存在します。
生命保険金請求権
まず、相続人の一人が受取人となっている生命保険金請求権は、相続財産を構成しません。
しかし、被相続人が保険料を支払っていた場合には、保険金請求権は保険契約に基づいて発生するものであって、贈与または遺贈であるとはいえないものの、共同相続人の一人が被相続人の保険料支払の結果として保険金請求権を取得するのは、他の相続人とのバランスを失するといえます。
そこで判例は、「保険金受取人である相続人とその他の共同相続人との間に生ずる不公平」が「903条の趣旨に照らし到底是認することができないほどに著しいものであると評価すべき特段の事情が存する場合には」、「同条の類推適用により、当該…保険金請求権は特別受益に準じて持戻しの対象となる」とします。
すなわち、保険金請求権は特別受益にあたらないけれども、「特段の事情」(※保険金の額、この額の遺産の総額に対する比率や、同居の有無、被相続人の介護等に対する貢献の度合いなどの保険金受取人である相続人及び他の共同相続人と被相続人との関係、各相続人の生活実態など様々な事情を考慮します)がある場合には、特別受益に準じた扱いをするということになります。
死亡退職金
死亡退職金も、生命保険金請求権と同様、相続財産を構成しません。これについて、死亡退職金は被相続人が受けるはずだった賃金の後払いの性質を有するものであるから、特別受益にあたるとの見解があります。
しかし、死亡退職金が受給権者の生活保障を目的とした制度に依拠して支出されるものであることを考慮すれば、これを特別受益とみることには問題があるといえます。
そこで生命保険金と同様、共同相続人間に生じる不公平が903条の趣旨に照らし到底是認することができないほどに著しいものであると評価すべき特段の事情が存する場合に限り、特別受益に準じた扱いをするべきといえます。
特別受益考慮の方法
特別受益を受けた共同相続人がいる場合、その受益をどのように考慮すべきかは、相続における平等性を実現するための重要な要点です。以下、評価や具体的な算定方法、持戻し免除の意思表示について解説します。
特別受益の評価
特別受益の評価は、被相続人の死亡時点での価値に基づいて行います。この評価は、相続財産として考慮されるべきものとしての価値と、特別受益として考慮されるべきものとしての価値の差を明らかにすることが求められます。この評価には、専門家の鑑定や証拠資料をもとに行われることが多いです。
具体的相続分の算定例
例えば、A、B、Cの3人が共同相続人で、総相続財産が3000万円の場合、平等に分ければ一人あたり1000万円です。しかし、Aが特別受益として600万円を受け取っていた場合、その600万円をAの相続分から控除する形で考慮します。
その結果、Aの取得分は600万円、BとCの取得分はそれぞれ1200万円となります。このように、特別受益を考慮した上で相続分を算定します。
持戻し免除の意思表示とは?
持戻し免除の意思表示とは、被相続人が特定の相続人に対して特別受益を与える際に、その特別受益を相続時に持戻ししないことを明示的に意思表示することを指します。
この意思表示があった場合、特別受益として考慮されず、通常の相続財産として取り扱われます。このため、持戻し免除の意思表示があるかどうかを確認することは、相続時の取り決めや紛争の回避のために非常に重要です。
特別受益を弁護士に相談した場合の費用
遺産分割において特別受益の主張を弁護士に依頼する場合、以下のような費用となっております。
着手金
交渉 27万5,000円〜
調停 38万5,000円〜
審判・訴訟 49万5,000円〜
報酬金
27万5,000円+経済的利益の11%
※上記を原則としながらも、事案によって増減させていただきます。
実際にご相談いただくことで想定以上の金額が戻ってくる場合も少なくありません。泣き寝入りせず、まずはお気軽に無料相談をご利用いただければと思います。
寄与分とは
共同相続人の中に被相続人の財産の維持・増加に特別の寄与をした人がいるとします。この特別の寄与を考慮し、その相続人に対して特別に与えられる相続財産への持分のことを「寄与分」といいます(民法904条の2)。
そしてこの寄与分は、前述の特別受益以上に調停で主張される方が多いのですが、ほとんど認められていない印象です。
おそらく、寄与分というと、被相続人に対して何らかの貢献をすればいいというイメージしか持たれていない方が多いためだと思われます。
しかし後述のとおり、それは全くの誤りですので、この際そのイメージを取り払っていただければと思います。
寄与分はどのように決まる?
寄与分は、当事者の主張を待って、その存否及び額が判断されます。
家庭裁判所が遺産分割調停や審判において職権により介入し、寄与分の存否の判断をしてはならないことになっています。
また、寄与分は特別受益とは異なり、寄与の時期、方法・程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮して、裁量的に定められます。
寄与分が問題になるケース
相続において、一部の相続人が他の相続人よりも多くの寄与をしていた場合、その寄与に見合った相続分の増加を求めることができる「寄与分」が問題となります。以下、寄与分が特に問題となる具体的なケースについて解説します。
家業に従事していた
家族が経営する事業や店舗に一部の相続人が従事しており、他の相続人よりも多くの時間や労力を投じていた場合、その寄与を評価する必要が生じます。特に、相続人が家業の発展や継続のために多大な貢献をしていた場合、寄与分の要求が正当とされることが多いです。
親への仕送りを行なっていた
親が高齢や経済的に困難な状況にあり、一部の子供が定期的に経済的なサポートや仕送りを行っていた場合、その子供の寄与が評価される可能性があります。このようなケースでは、仕送りの金額や期間、親の生計を支えるための貢献度などが考慮されます。
親の介護をしていた
親の介護を主に担当していた子供がいる場合、その子供の寄与を相続分に反映させることが考えられます。介護の期間、その内容や重さ、他の兄弟姉妹との役割分担などが評価のポイントとなります。特に、長期間にわたり、他の家族の協力を得られずに介護を続けていた場合、その寄与は大きいと認識されることが多いです。
寄与分として考慮されるには?
家庭裁判所により裁量的に定められるといっても、寄与分として主張すれば何でもそれが考慮されることにはなりません。以下に述べるとおり、いくつかの要件を満たす必要があります。
特別の寄与であること
寄与分として考慮されるには、その寄与が「特別の寄与」であると評価されるものでなければなりません。
つまり、被相続人との身分関係に基づいて通常期待される程度を超える特別の貢献をしたことが求められるのです。
例えば、「自分は他の相続人よりも、被相続人の面倒をよく看てきたのだ」と主張したとしても、それが夫婦間の同居・協力・扶助義務、直系血族・兄弟姉妹間の扶養義務により通常期待されている範囲を超えるものでなければ、「特別の寄与」とは評価されません。
裁判例においても、妻の寄与分の主張に関して、
- 「遺産形成についての他方配偶者の寄与に関して考えるならば、夫婦の協力義務にもとづく一般的な寄与にもとづき、寄与配偶者の遺産中に占める潜在的な持分は、相続分の形で定型化されているものと考えられるので、一般的な寄与をしたことを根拠として、寄与配偶者に対し法定の相続分以上の遺産を取得させることはできない」
としたものがあります。
したがって、一般の方がイメージされているよりも、「特別の寄与」のハードルは高いといえますので、この点はよく覚えておいていただきたいと思います。
寄与が無償であること
寄与分として考慮されるには、寄与行為に対する対価や補償を受けていないことも必要です。
もっとも、寄与行為をした相続人自身に対して何らの贈与がなされていなくても、その者の配偶者や子に対してなされているという場合もあります。
その場合は、贈与の経緯や贈与された物の価値・性質・当該贈与により寄与行為をした相続人が受けている利益等を考慮し、その贈与が実質的にみて寄与行為者に対するものと異ならないか否かを検討する必要があります。
被相続人の財産の維持・増加への寄与であること
寄与分として考慮されるには、被相続人の財産の維持又は増加についての寄与でなければなりません。
「特別の寄与」があったとしても、それは、被相続人の財産の維持又は増加と因果関係があるものでなければなりません。
したがって、単なる精神的な支援だけでは寄与分の対象となりませんし、被相続人の療養看護や身辺の世話に対して特別の貢献をしたからといってそれが被相続人の財産の維持又は増加につながっていなければ寄与分の対象とはなりません。
反対に、被相続人の財産の維持又は増加にあたるものであれば、その寄与の態様は問われません。
特別受益や寄与分のことは、弁護士にご相談を!
以上、特別受益や寄与分について概要を説明致しましたが、その判断は非常に専門的なものといえます。
特別受益や寄与分の主張に際しどういう資料が必要となるのか、そもそも、具体的にどういうものが特別受益にあたるのか、どういう行為が寄与分にあたるのかはその個別の相続事案ごとに判断するほかありません。
こうした判断を法律の専門家以外がおこなうのは至難であるといえますし、本人では気づいていないもので特別受益や寄与分として主張できるものがある場合もあります。したがって、特別受益や寄与分のことは、法律の専門家である弁護士に相談するのが得策であるといえます。ここまで読んでいただいた方の中には、特別受益や寄与分について、これまで抱いていたイメージとは全く異なると感じた方もいらっしゃるかもしれません。
それほど、特別受益や寄与分については、一般的に持たれているイメージと法律の考え方が離れているといえます。この点、相続問題を弁護士に相談すれば、特別受益や寄与分、その他の問題点について漏れなく検討し、最適な解決が可能となります。
「他の相続人が生前利益を受けていたみたいだが、これは特別受益にあたらないのだろうか」、「自分は被相続人の生前、たくさんの貢献をしたがこれは寄与分として考慮されないのだろうか」などとお悩みの方は、ぜひ当事務所までご相談ください。