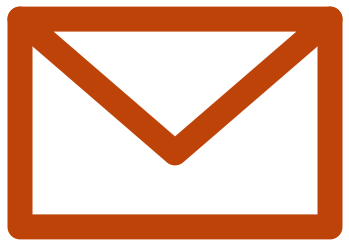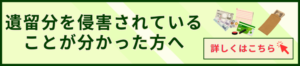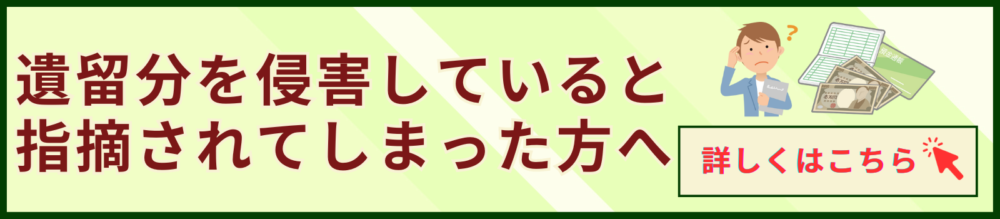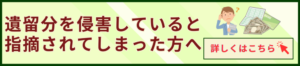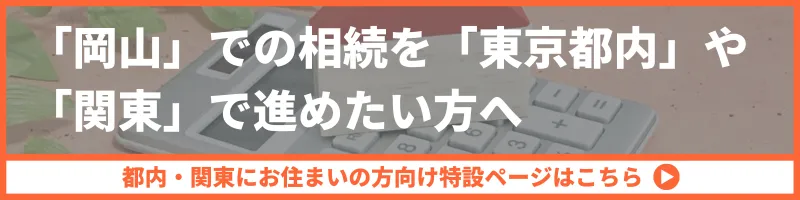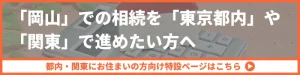遺留分の権利者でなくなる場合について弁護士が解説


相続には「遺留分」といって、一定の法定相続人には最低限相続できる割合が定められています。遺留分には、家族を失った相続人の生活を守るための保障といった意味合いもあります。この遺留分があるため、仮に遺言書によって1人の相続人に「すべての財産を相続させる」といった記載があったとしても、遺留分については後から請求することが認められています。これを法律の世界では、「遺留分侵害額請求(旧遺留分減殺請求)」といいます。
しかし、事情次第では遺留分の権利者でなくなってしまうことがあります。となれば当然、遺留分の請求はできなくなり、最低限度の保障もなくなってしまうのです。では、どういった場合に遺留分の権利者でなくなってしまうのでしょうか?今回は、遺留分の権利者でなくなる場合について詳しく解説していきます。
目次
遺留分の権利者でなくなる場合
遺留分の権利者でなくなるのは、主に以下の5つの場合となっています。
①相続放棄をした場合
⓶遺産分割協議が完了した場合
③相続欠格に該当する場合
④相続廃除がされた場合
⑤胎児が出生しなかった場合
相続放棄をした場合
相続放棄をした場合、はじめから相続人ではなかったことになります。よって、遺留分の権利者としての資格も、当然ながら失ってしまいます。
相続放棄は、遺産がプラス財産よりもマイナス財産のほうが多い場合によく利用される手続きですが、遺留分の権利も失われてしまいます。一度した相続放棄を取り消すことは原則としてできない上に、自身に相続があったことを知ったときから3カ月以内に申述する必要があることからも、利用の際は慎重に検討する必要があると覚えておきましょう。
相続開始前の遺留分放棄
相続放棄とよく似た手続きに、相続開始前に家庭裁判所の許可を得ることできる「遺留分放棄」という手続きがあります。遺留分放棄は相続人ではなくなってしまう相続放棄とは異なり、たとえ遺留分放棄をしたとしても、相続開始後、遺産分割によって遺産の取得は可能です。単に遺留分を請求する権利を自ら放棄する、という手続きです。
ただし、相続放棄とは異なりマイナス財産も承継してしまうため、事情次第では被相続人が亡くなった後、改めて相続放棄の手続きを取らなければならない点に注意です。遺留分放棄と相続放棄は、名前は似ていますがまったく性質の異なる手続きです。
相続開始後の遺留分放棄
相続開始後に遺留分放棄をしたい場合は、家庭裁判所での手続きは必要ありません。遺留分というのは、遺留分侵害額請求権を行使しないのであれば、特段効力が生じるものはないため、そのまま何もしないことが遺留分を放棄したことになります。
ただし、相続人の間で遺留分の行使について確認したいなど、特別な事情がある場合は、遺産分割協議書にて遺留分権を行使しない(放棄する)旨を記載するのが有効です。
遺産分割協議が完了した場合
遺産分割協議に参加し、相続人全員が合意した場合は、後になってから遺留分を請求することは原則としてできません。
たとえば、遺産分割協議の際に「自分は遺産などいらない」、といって相続分の取得を拒否した場合、後になって「やっぱり遺留分を請求したい」といったことは不可能となっています。もちろん、遺留分だけなく遺産の再分割を求めることもできないため、遺産分割協議の内容は慎重に判断するよう心掛けてください。
相続欠格に該当する場合
相続欠格に該当する場合、相続人としての地位に加え、遺留分権も失ってしまいます。
具体的には、以下に該当する場合に相続欠格となります。
・故意に被相続人、同順位の相続人を死亡させた、死亡させようとした場合
・被相続人が他者に殺害されたのを知りながら、告発や告訴をしなかった場合
・詐欺や脅迫などによって、被相続人の自由意志による遺言作成を妨げた場合
・見つかった遺言書を隠蔽・破棄、もしくは中身の偽造・変造等した場合
なお、相続欠格はなにかしらの手続きが必要なわけではありません。上記に該当する行為があった場合、その時点でただちに相続権・遺留分権を失うことになっています。
相続廃除がされた場合
被相続人によって相続廃除がされた対象者は、相続人としての地位に加え、遺留分権も失ってしまいます。相続廃除には、被相続人が生前に家庭裁判所に申し立てる方法と、遺言で意思表示を示し、遺言執行者が家庭裁判所に申し立てるという2つの方法があります。
相続廃除が認められるには、相応の理由が必要とされています。具体例を出せば、「長年家庭内で暴力を振るっていた」、「自身の預金を勝手に使い込まれていた」、「重大な罪を犯して家族に迷惑をかけた」などといった場合に認められることになっています。
なお、相続廃除は対象者のみに効力がおよぶため、すでに対象者が亡くなっていて、子どもが代襲相続する場合、その子どもの相続権・遺留分権まで失われることはありません。
胎児が出生しなかった場合
民法によると、原則として胎児に権利能力はありません。
その一方で、胎児には相続権が認められています。「胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす」と規定されているためです。それゆえ、胎児には他の相続人らと同様に遺留分権もあると考えられています。よって、相続開始時に胎児だった相続人にも、出生後に遺留分侵害額請求を行使する権利が認められています。しかし、胎児が無事に出生しなかった場合は、上記の規定は適用されないことになっています。
そもそも遺留分がない被相続人の兄弟姉妹と包括受遺者
上記はいずれも遺留分の権利者でなくなる場合です。一方で、相続人としての地位がありながら、被相続人の兄弟姉妹には遺留分が認められていません。
また、相続人と類似した立場にある包括受遺者にも遺留分は認められていません。包括受遺者とは、遺産の全部、または一部を包括的(特定されない状態で)に遺贈された者です。
被相続人の兄弟姉妹と包括受遺者には、そもそも遺留分権が認められていないため注意しましょう。
遺留分侵害額請求をされたい場合は弁護士にご相談ください
以上が遺留分の権利者でなくなる場合についてです。しっかり注意を払っていれば、遺留分権が失われる心配はまずないと言えるでしょう。しかし、遺留分権が失われないことと、侵害された遺留分を請求するのとでは、まったく意味が異なります。遺留分侵害額請求をしたい場合は、侵害している相続人、もしくは受遺者と交渉をする必要があります。事情次第では、調停や裁判といった手続きも視野に入れなければなりません。
もし、遺留分侵害額請求をご検討中の方がいましたら、弁護士への相談をおすすめします。
弁護士であれば、あなたに代わって交渉の席に着くことができるばかりか、調停や裁判といった手続きも任せることができます。当事務所においては、遺留分侵害額請求を実現させた実績が豊富にあるため、どうか安心・信頼してご相談ください。