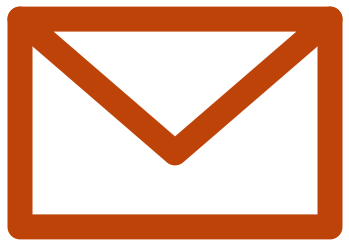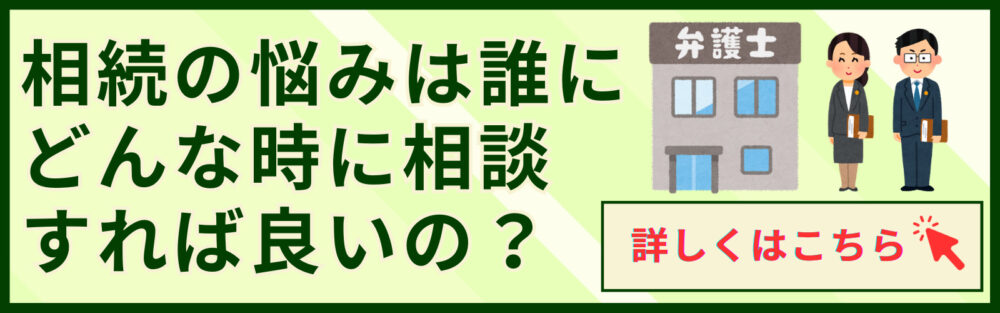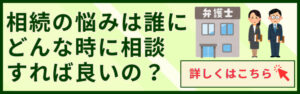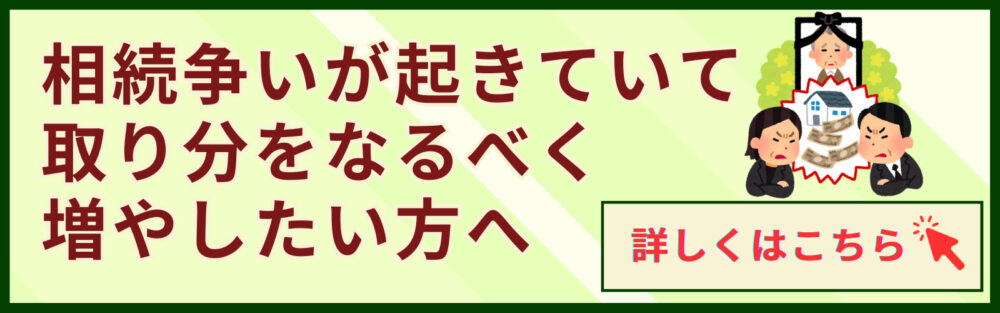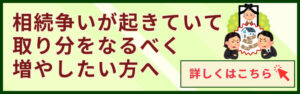遺産分割協議後に遺言が発見されたら?効力や協議のやり直しについて弁護士が解説
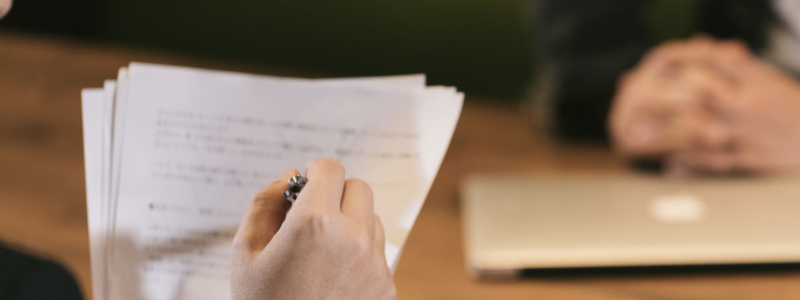

相続というのは、当初は想定していなかったトラブルが起こりやすいものです。
たとえば、遺産分割後に遺言書が見つかったとしたら、どのように対応すべきでしょう?また、その遺言書に効力はあるのでしょうか?
すでに終了しているはずの遺産分割は、またやり直さなければならないのか?それとも、遺言書を無視することなどできるのでしょうか?というわけで今回は、遺産分割後に遺言書が見つかった場合の対応について、詳しく解説していこうと思います。


目次
形式別あとから遺言書が見つかった場合の対処
遺産分割後に遺言書が見つかるというのは、決してめずらしいことではありません。
なぜなら、遺言書というのは生前に書くものでありながら、効力が生じるのは死後となっています。生前であれば、内容を他者に見られたくないと感じるのが当然です。それゆえ、遺言書をわかり難い場所に置いている方も多く、死後すぐには見つからず、遺産分割後に見つかってしまったというケースが、現実にはよく起こり得ます。そして、遺言書というのは死後何年経過していたとしても無効になることはありません。よって、たとえ遺産分割後であっても、遺言書が見つかった以上、そのまま無視するわけにはいかないのです。
遺産分割後に遺言書が見つかった場合は、見つかった遺言書がどの形式であったかによって若干対応が異なることになります。以下にてさらに詳しく見ていきましょう。
公正証書遺言の場合
見つかった遺言書が公正証書遺言だった場合、遺言執行者について記載されている可能性が高いです。
もし、遺言執行者が記載されている場合、すでに遺産分割を終えていたとしても、一度すべての財産を戻し、遺言執行者先導の元、再度遺産分割をしなければなりません。
とはいえ、現実には遺言執行者がすでに亡くなっている場合や、遺言執行者への選任を断るケースもあるため、ケースバイケースな対応が必要となっています。もし、遺産分割後に公正証書遺言が見つかった場合は、弁護士への相談をおすすめします。
なお、遺言執行者についての記載がなかった場合でも、一度した遺産分割はすべて無効となります。通常、公正証書遺言の場合、後述する自筆証書遺言とは異なり、検認手続きを経る必要はありません。また、遺言書の作成には公証人が携わっているため、原則的には遺言書が法的不備によって無効になることはありません。
自筆証書遺言の場合
見つかった遺言書が自筆証書遺言だった場合、まずは検認手続きを経る必要があります。
検認手続きとは、家庭裁判所にて見つかった遺言書の形状や内容等を明確にし、保存するために行われる手続きで、自筆証書遺言の場合は必ず行わなければなりません。
ただし、遺言の検認手続きは、遺言書の有効・無効を判断する手続きではないため、仮に検認手続きを経た遺言書であっても、法的不備があれば無効となります。よって、自筆証書遺言が見つかった場合は、検認手続きを経た後に、遺言書の有効・無効を改めて判断する必要があります。しかし、素人目に遺言書の有効・無効を判断するのは非常に危険であるため、遺言書持参の上、弁護士への相談をおすすめします。
なお、自筆証書遺言の場合も、遺言執行者について記載されているケースもあります。
秘密証書遺言の場合
見つかった遺言書が秘密証書遺言だった場合、まずは検認手続きを経る必要があります。
秘密証書遺言は、その内容を誰にも知られることなく作成できますが、遺言の存在自体は公証人と証人が関与して証明されている形式です。したがって、遺言書自体の効力を確認するためには、家庭裁判所で検認手続きを行い、遺言書の形状や内容が確認されます。
秘密証書遺言は、公証人が遺言書を預かっているわけではなく、遺言者が自身で保管しているケースがほとんどです。そのため、遺産分割後に秘密証書遺言が見つかることも珍しくありません。検認手続きを行った後、遺言内容が法的に有効と判断されれば、遺言書の内容に基づいて再度遺産分割を行わなければなりません。
遺言執行者が記載されている場合は、その執行者が遺言に従って財産分割を進めますが、記載がない場合や執行者が不在の場合には、遺産分割を再度行うための対応が必要です。
いずれにせよ、秘密証書遺言が見つかった場合も、法的な判断や対処が複雑になることがあるため、弁護士に相談することを強くおすすめします。
既に終わった遺産分割はどうなる?
遺産分割をやり直す必要がないパターン
新たな遺言書が発見された場合は、まずは内容を確認し、自筆証書遺言であれば検認手続きを経る必要があります。
そして、遺産分割をやり直す必要があるのか、やり直す必要がないのかについては、見つかった遺言書が法的に有効と言えるのかに加え、相続人全員の意思が重要となってきます。もし、遺言書が法的に有効なもので、相続人の中に1人でもやり直しに賛成しているのであれば、必ず遺産分割をやり直す必要があります。
また、遺言書によって新たな受遺者がいる場合は、受遺者も含めた全員の意思が揃わない以上、遺産分割はやり直さなければなりません。
とはいえ、すでに分割された遺産を元通りにするというのは簡単なことではありません。前述したように、遺言書は死後何年経過していたとしても有効とされてはいますが、現実には何年も経過していれば再分割が困難なケースも存在します。しかし、見つかった遺言書が法的に有効であれば、無視するわけにはいかないのも事実です。こういった場合は、すぐに弁護士に相談し、対応について的確なアドバイスをもらうのが良いでしょう。
遺産分割をやり直す必要があるパターン
上述したとおり、相続人の中で1人でも遺言書どおりに遺産分割したいと考えているのであれば、遺産分割をやり直す必要があります。
そもそも遺言というのは、亡くなった方の最後の意思であることから、民法にて記載されている法定相続分に基づいた相続より優先されるべきとされています。よって、すでに遺産分割が終わっていても、遺言書が見つかり、1人でもやり直したいと考える相続人がいれば、遺産分割は必ずやり直さなければなりません。
また、遺言書に相続人以外の受遺者(遺言によって遺産を受け取る権利がある者)がいる場合も、受遺者を含めた全員の同意がない限り、遺産分割はやり直さなければなりません。
遺言書があとから出てきた場合、相続放棄は可能か
遺産分割が完了した後、遺言書が新たに発見された場合、相続放棄ができるかどうかは状況によって異なります。相続放棄は、法律上原則として相続開始を知った日から3ヶ月以内に行わなければなりません。この期間を過ぎると、通常は相続放棄は認められないため、遺産分割後に遺言書が発見された場合でも、3ヶ月の期間が過ぎていると相続放棄を行うことは難しくなります。
しかし、例外として、相続放棄の3ヶ月の期間が過ぎていても、相続人が相続財産の状況を正確に把握できなかった場合や、遺言書の存在が相続人に全く知らされていなかったような特殊な事情がある場合、家庭裁判所に申し立てることによって期間を延長できる場合もあります。このようなケースでは、相続放棄の申立てが認められる可能性もあります。
他の相続人が遺言書を隠していた場合はどうすればいい?
遺産分割が終わった後に、他の相続人が遺言書を故意に隠していたことが発覚するケースも少なくありません。
このような場合、遺言書を隠していた相続人の行為は法的なトラブルとして扱われること可能性が高いです。
まず、遺言書の存在を隠すことは、相続手続きの正当性を大きく損なう行為であり、場合によっては相続欠格とみなされる可能性があります。相続欠格とは、特定の重大な不正行為を行った相続人が相続権を失うことを指し、遺言書を意図的に隠す行為もその対象となり得ます。したがって、遺言書を隠していた相続人は、遺産を受け取る資格を失うことがあり、その点について法的な手続きが取られることが一般的です。
また、隠されていた遺言書が発見された場合、たとえ遺産分割が既に完了していたとしても、その分割内容は無効となる可能性が高いです。遺言書の内容に基づいて、再度財産の分割を行わなければならなくなります。遺産分割協議が他の相続人によって不正に操作されていたと判断される場合、最初の遺産分割自体が無効となり、隠された遺言書に基づいて新たに遺産分割が進められることになります。
さらに、このような事態に陥った場合は、遺言書を隠していた相続人に対する民事上の損害賠償請求や、場合によっては刑事告訴も検討されます。相続問題が複雑化する可能性が高いため、早急に弁護士に相談し、適切な対処を講じることが重要です。
他の相続人による不正行為が疑われる場合には、遺言書の有効性や適切な法的手続きを確保するため、法的なアドバイスを受けながら迅速に対応を進めることが肝要です。
遺産分割後に遺言書が見つかった場合は弁護士にご相談ください
遺産分割後に遺言書が見つかった場合、中身や他の相続人・受遺者の意思によっては遺産分割をやり直さなければなりません。
遺言の内容が自身に不利な内容であれば、やり直したくないと感じるのも無理はありません。しかし、遺産分割をやり直したくないがために、遺言書を隠してしまったり、内容を改変・偽造したりしてしまえば、相続権そのものが剥奪されてしまう恐れがありますし、その逆もまた然りです。
もし、遺産分割後に遺言書が見つかって、不安に感じているという方は、まずは当事務所にご相談ください。見つかった遺言書の法的不備についてはもちろん、他の相続人・受遺者との交渉など、様々な観点からあなたが有利になるようサポートさせていただきます。お気軽にご相談ください。