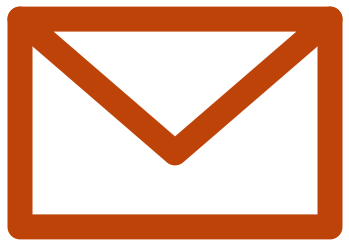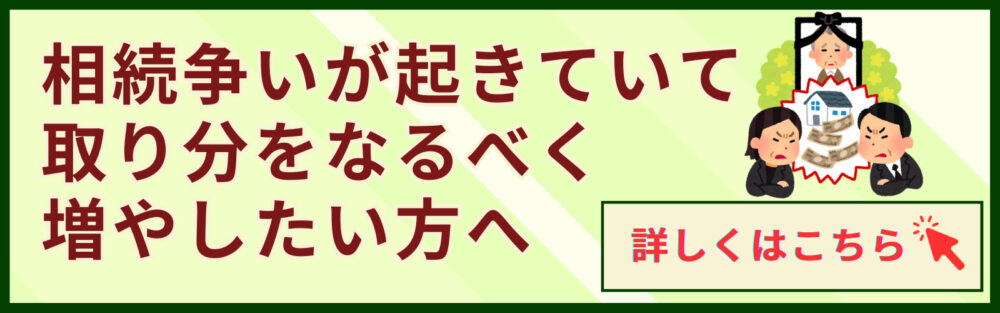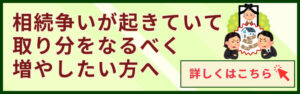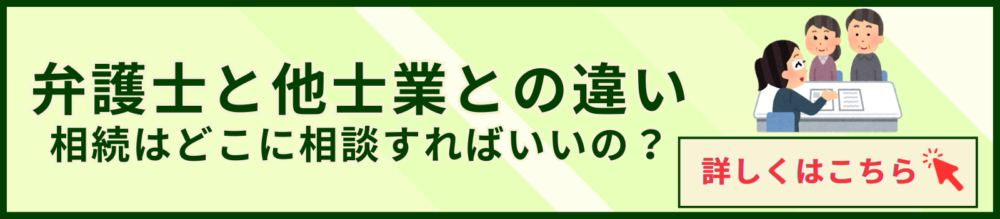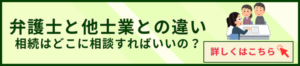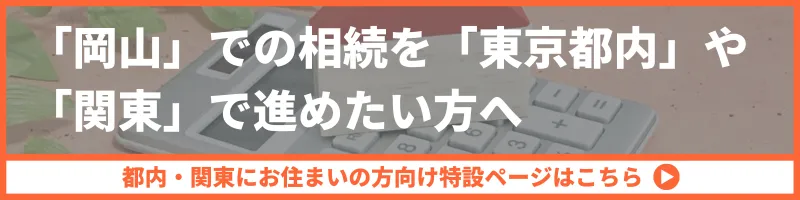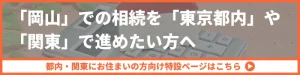不公平な遺言は無視しても良いの?不利な相続の対処法を解説
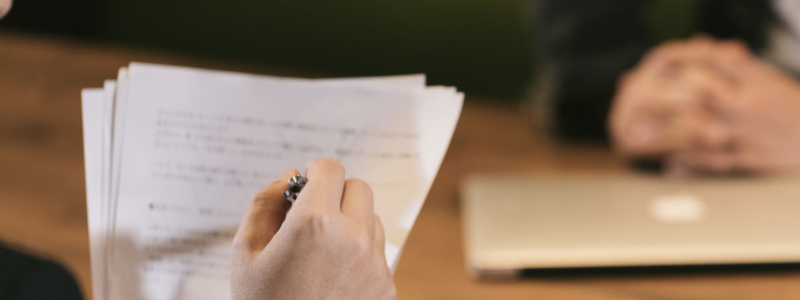

故人の遺言を家族で確認した際、以下のようなお悩みをお持ちではないでしょうか。
・特定の相続人に財産の全て(もしくは大半)を相続すると書かれている
・兄弟間で遺言の解釈が異なる
今回は、不公平な遺言を残されてしまったときの対処方法について解説いたします。
目次
遺言書は無視して良いの?
無視するだけでは罰則になりません
ご相談者様が遺言書の内容を知りつつ、それを意図的に無視する行為は、直接的な罰則の対象とはなりません。
ただし、遺言書に従わないことで生じる遺産分割のトラブルや紛争は、後に大きな不利益につながる可能性があります。そのため、一方的に遺言を無視したり、遺言書と異なる主張を他の相続人にぶつけるといった行為はおすすめできません。
有効だからといって、すべてが受け入れられるわけではありません
遺言書が法的に有効であったとしても、その内容がすべて無条件に受け入れられるわけではありません。
日本の相続法では、法定相続人に一定の最低限の取り分(遺留分)が保障されています。つまり、遺言の内容がどれだけ一方的であっても、相続人はそれに異議を唱える法的手段を持っています。大切なのは、遺言の存在にひるまず、ご自身の権利を冷静に確認し、適切に対応することです。
偽造や破棄は刑事罰の対象になります
もし遺言書を偽造したり、遺言書を故意に隠したり破棄する行為に及んだ場合、これは刑事罰の対象となり得ます。また、相続人となる資格を失う(相続欠格)場合もあります。
これは法によって定められた犯罪行為であり、家族からの信頼を失ってしまうので絶対に避けるべきです。
遺言書ってどれくらいの効力があるの?
「遺言に書いてあれば何でもOK」は誤解──民法上の限界とは
「遺言に書かれているから仕方がない」と思い込んでしまう方も多いのですが、それは誤解です。
遺言の内容には民法上の制約があり、すべてが無制限に認められるわけではありません。たとえば、被相続人が生前に築いた財産すべてを特定の第三者に与えると記載していた場合でも、相続人には最低限の取り分(遺留分)を主張する権利があります。このように、遺言は万能ではなく、相続人には一定の保護が用意されています。
「遺留分」や「公序良俗」など、法的に制約される要素もある
遺言の内容が明らかに社会通念に反する場合、公序良俗違反として無効になる可能性があります。
たとえば、「不倫相手に全財産を相続させる」といった内容があった場合、その背景や事情によっては法的な問題が生じます。また、遺留分の侵害がある場合には、侵害された相続人が請求すれば、法的に取り戻すことが可能です。これらの制度は、遺言に対する歯止めとして機能しています。
よくある“誤解されがち”な遺言の効力範囲
「遺言に書かれている=絶対的な命令」と誤解されることは少なくありません。
しかし、実際には遺言に書かれていても無効となる場合があります。たとえば、自筆証書遺言で日付がなかったり、署名が欠けていたりすれば、その遺言は形式不備として無効になります。さらに、遺言で指定されていても、他の相続人の権利が完全に奪われるわけではありません。まずは専門家に確認することが肝要です。
遺言の内容がご相談者様にとって不利な際の対処法
遺言の内容があまりにも不公平であったり、最低限受け取ることができたはずの相続分にまで影響を及ぼしている場合は、法律的な手段を取ることも視野に入れましょう。
形式要件を満たしているか?有効性をチェック
遺言は、厳格な形式要件を満たさなければ効力を持ちません。
たとえば、自筆証書遺言の場合には全文・日付・署名が自書であること、押印があることが求められます。これらの要件を欠くと、遺言そのものが無効となる可能性があります。内容以前に、まず形式を確認することで、大きく展開が変わる可能性もあります。
自筆証書遺言が有効であったとしても、相続手続を進めるには家庭裁判所で「検認」手続きを行う必要があります。検認とは、遺言書の存在や状態を確認するもので、これを経ずに遺産分割を進めることはできません。なお、公正証書遺言についてはこの手続きが不要です。検認には時間がかかる場合もあるため、早期の準備が重要です
遺留分が侵害されていれば請求する
遺留分は、法律で保護された最低限の相続の権利です。
もし遺言によってこの遺留分が侵害されている場合、遺留分侵害額請求を行うことことで最低限の相続分を受け取るができます。
遺留分侵害額請求は、遺留分権利者が遺留分を侵害する遺贈や贈与を受けた相手に対して意思表示をするだけで十分とされています。しかし、後から「請求した」「請求されていない」といったトラブルを避けるためにも、「配達証明を付けた内容証明郵便」を使って請求を行うことが重要です。
遺留分侵害額請求が可能なケースや当事務所の解決事例はこちらのページでも解説しておりますので併せてご覧ください。
遺言無効確認の訴訟を起こす
遺言の無効を主張し訴訟を起こすことも一つの方法です。
これは無効の理由が明白である場合に有効な手段となります。遺言書が無効となるケースには下記のようなものがあります。
日付や氏名が適切に書かれていない
遺言書には日付や氏名が正確に記されている必要があります。例えば「○月吉日」のように日付が特定できないなど、定められた書き方ではない場合は無効と判断されてしまいます。
代筆されている
自筆証書遺言の場合、全文、日付、氏名が本人によって書かれている必要があります。代筆された部分があると、それが理由で遺言書が無効となってしまいます。
被相続人(作成者)に意思能力がなかった
作成時に被相続人に意思能力がなかった場合、たとえば認知症などによって自己の意思を明確に表現できない状態であれば、遺言は無効となる可能性があります。
公正証書遺言であれば公証人が関わりますので、自筆の遺言書よりも無効となる可能性が少ないです。
しかし、例えば遺言をする能力が十分でない状態で口授したときや、口授そのものがきちんと行われないまま遺言書が作られたときなどは、無効だと主張することができるかもしれません。
相続人全員で無効だと合意した
遺言書に対して相続人全員が無効であるとの合意が得られた場合には、その遺言書は法的効力を失います。
しかし、遺言が無効になることで不利益を被る人がいれば合意を得ることは難しく、争いの種になる可能性もあるため、慎重に提案する必要があるでしょう。
状況によっては、遺言書に記載された内容が遺産分割協議よりも優先される場合があります。
- ①遺言書で、遺産分割を禁じられている場合
- ②遺言執行者が選任されている場合
- ③相続人以外の第三者へ遺贈がされる場合
上記のような場合は、相続人全員の同意があっても、遺言の内容が優先されることが原則となります。
これらの基準に当てはまっているかもしれない遺言があれば早急に弁護士へ相談することをお勧めいたします。
感情面でも金銭面でも損しないための具体的戦略
遺産分割協議の場で“声を上げられる根拠”を持つ
遺産分割協議は、相続人全員の合意が必要なプロセスです。
不利な遺言が存在する場合でも、それに対抗する法的根拠を理解していれば、交渉の場で正当な主張を行うことが可能です。たとえば、「遺留分侵害額請求権」や「遺言無効確認訴訟の検討」など、明確なカードを持って臨むことで、他の相続人に対しても説得力を持って交渉を進めることができます。
法律の理解と準備が、精神的にも優位に立つための鍵となります。
「他の相続人と交渉しづらい」と感じたら、すぐに弁護士へ
遺言の内容が争点となる場面では、相続人同士の感情的対立が激化することも少なくありません。
「話が通じない」「一方的に手続きを進められている」と感じたら、早い段階で弁護士に相談することをおすすめします。弁護士が介入することで、法的根拠に基づいた交渉が可能になり、感情的な対立を緩和することにもつながります。
時間が経つほどに選択肢が減っていくこともあるため、迷ったときこそ、早期相談が重要です。
話し合いの中で“主導権”を取るための準備とは
遺産分割協議で主導権を取るには、事前の情報収集と法的知識の備えが不可欠です。
遺言書の有効性チェック、相続財産の把握、他の相続人の状況分析など、準備の段階でどれだけ戦略を立てられるかが、結果に大きな影響を与えます。また、証拠となる書類や記録を事前に整理しておくことで、議論の主導権を握ることが可能になります。弁護士との綿密な連携により、相手の出方を読みながら柔軟に対応していくことが大切です。
遺留分侵害請求の期限は1年──悩んでいる時間はありません
遺留分侵害額請求権には「相続開始および遺留分侵害を知った時から1年以内」という明確な時効があります。
つまり、「様子を見てから考えよう」と先送りしていると、知らないうちに請求権を失ってしまう可能性があるのです。気になる遺言があった場合には、できるだけ早く内容を確認し、弁護士に相談して請求の準備を進めることが、自身の権利を守るうえで極めて重要です。
よくある相談パターンとその対処のヒント
「生前は平等と言っていたのに、遺言が全然違う」
「生前、親は“みんな平等に分ける”と言っていたのに、遺言書では特定の相続人に偏った内容だった」という相談は非常に多く寄せられます。
生前の言動が証拠として残っていない限り、法的には遺言書の内容が優先されることになりますが、納得できない場合には「遺留分侵害額請求」や「遺言無効確認訴訟」を検討する余地があります。法的手段により、ある程度までバランスを取り戻すことが可能です。
「他の相続人が遺言を盾に独占的に進めてくる」
一部の相続人が「遺言書に書いてあるから従え」と強硬に主張し、他の相続人の意見を無視して手続きを進めようとするケースもあります。
このような状況に置かれた場合、自分の立場が弱いと感じてしまいがちですが、遺産分割協議や法的請求によって自分の権利を主張することが可能です。弁護士が介入することで、対話の場を法的に整えることができ、話し合いを有利に進められるようになります。
「親の意思ではなく、特定の兄弟が誘導したのでは?」
高齢の親と長期間同居していた兄弟が、親に働きかけて都合の良い遺言を作成させたのではないかと疑われるケースも少なくありません。
このような場合には、遺言の有効性そのものに疑問を持つ必要があります。筆跡鑑定、診療記録の精査、介入時期の調査などにより、遺言作成時の状況を明らかにすることが重要です。不審な点があれば、すぐに弁護士と共に事実確認に乗り出すべきです。
自分の取り分が少ないと感じた場合は弁護士へご相談ください
泣き寝入りする必要はありません──法的な救済手段は存在します
遺言書が見つかり、その内容に驚きや怒りを感じたとしても、泣き寝入りする必要はありません。民法上、相続人には遺留分という最低限の権利が保障されていますし、遺言の有効性自体に疑問がある場合には訴訟で争うことも可能です。重要なのは「遺言書=すべて正しい」と思い込まず、冷静に状況を分析する姿勢です。
ご相談者様にとって有利に進めるための「初動」がカギ
遺言が絡む相続問題では、最初の対応が非常に重要です。遺言書の内容に目を通す段階で疑問点を持ったら、まずは法的な視点から妥当性を検証することが必要です。勢いに任せて他の相続人に従ってしまうと、取り戻せない不利益を被ることもあります。まずは一度、状況を整理するために専門家に相談してください。
まずは無料相談で、遺言の有効性や戦略を見極めましょう
遺言に関するお悩みや遺留分侵害額請求についての相談は、西村綜合法律事務所にお気軽にご相談ください。地元岡山に密着し、多数の相続トラブルの解決実績を持つ経験豊富な弁護士が所属しています。
西村綜合法律事務所では岡山にお住まいの皆様向けに無料相談を実施中です。遠方の方、事情がありご来所が難しい方向けにオンライン面談も行っております。