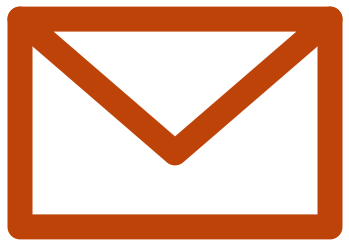故人と同居していて生前贈与を受けているのですがこれは特別受益にあたりますか?
生前贈与は原則として特別受益に該当します
生前贈与とは、被相続人が生前に相続人へ財産を贈与することを指します。
民法上、特定の相続人が生前に受けた贈与は、遺産分割の際に公平性を保つため「特別受益」として扱われることが多いです。これにより、他の相続人との間で不公平が生じないように調整が行われます。
特別受益に該当する贈与
相続人の結婚に伴う贈与
被相続人が相続人の結婚を支援するために多額の資金を贈与した場合、これは特別受益に該当する可能性があります。例えば、新婚生活のための住宅資金援助や結婚式費用の負担などが該当します。
相続人の養子縁組のための贈与
相続人が養子縁組をする際に、被相続人が養育費や教育資金を特別に提供した場合も特別受益とみなされることがあります。これは、一般的な養育費を超えた金額が贈与された場合に適用されることが多いです。
扶養義務の範囲を超えた贈与
被相続人が相続人に対して、通常の生活費や学費の負担を超える多額の財産を贈与した場合、特別受益と見なされることがあります。例えば、高額な不動産を生前に譲渡していた場合や、多額の現金を贈与していた場合などが該当します。
長年にわたって同居していたことによる家賃相当額はどのような扱いですか?
長年にわたる同居に関しては、特別受益とは認められない可能性が高いと考えられます。裁判所の判断としても、単に家賃を支払わずに親と同居していたという事実だけでは、特別受益に該当するとまではいえないケースがほとんどです。
特に、同居していた相続人が親の介護や生活支援を行っていた場合、その精神的・肉体的な負担が考慮され、むしろ「寄与分」として認められる可能性が高まります。つまり、同居によって相続人が恩恵を受けたとみなされるよりも、親の生活を支えたという評価が優先されることが多いのです。
また、同居によって親の財産が著しく減少した場合や、同居人が親の資産を自由に使用していた場合は別ですが、そうした事情がない限り、「遺産の移動はなかった=生前贈与にはあたらない」と判断されることが一般的です。例えば、親が生活費のすべてを負担していた場合でも、それが通常の扶養義務の範囲内であれば、特別受益として扱われることはほとんどありません。
特別受益に該当したら遺産相続はどうなる?
特別受益の持ち戻しを行う
特別受益が認められた場合、その相続人は「すでにもらったもの」として特別受益相当額を遺産総額に加えた上で遺産分割を行うことになります。例えば、相続財産が1,000万円で、ある相続人が生前に300万円の贈与を受けていた場合、遺産総額は1,300万円として計算されます。そして、この相続人はすでに300万円を受け取っているため、残りの遺産分割では不公平にならないよう調整されます。
被相続人が持ち戻しに反対すれば行われません
ただし、被相続人が「この生前贈与は特別受益として考えない」と意思表示していた場合、特別受益の持ち戻しは行われません。この意思は通常、遺言書などの明確な形で示されることが望ましいです。例えば、遺言書に「この贈与は相続財産の一部として考えない」と明記されていれば、特別受益の持ち戻しを回避できます。
相続・遺産分割のトラブルは西村綜合法律事務所へご相談ください
特別受益が認められるかどうか、また遺産分割にどのような影響を与えるのかについては、ケースごとに異なります。相続人間のトラブルを未然に防ぐためにも、専門家のアドバイスを受けることが重要です。
西村綜合法律事務所では、相続・遺産分割に関するご相談を承っております。初回相談は無料で、オンライン面談にも対応しておりますので、相続に関するお悩みがある方はお気軽にお問い合わせください。