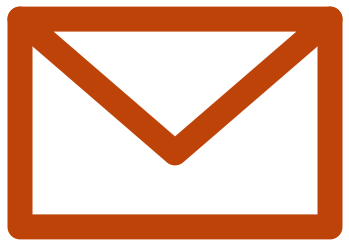相続財産に会社(株式)が含まれる場合の兄弟間トラブル、経営権の分配と紛争を避ける方法について
相続財産の中に会社の株式が含まれる場合、兄弟間で大きな対立が生じやすいことをご存じでしょうか。会社は通常の不動産や預金と異なり、経営権や意思決定に直結するため、単純に分割すればよいというものではありません。
本ページでは、兄弟が株式を相続した場合に起こりやすい具体的なトラブル、遺産分割調停へ発展するリスク、その際の株式評価や買い取りの難しさについて解説します。
株式の相続・遺産分割が発生しそうな方および既に発生している方にぜひお読みいただきたい内容です。


目次
会社は相続できるの?兄弟で株式を持つと何が起きるか
会社そのものではなく「株式」が相続対象になる
会社は法人であり、相続財産となるのは会社自体ではなく、被相続人が所有していた株式(または持分)です。
株式を相続することで、その株主としての権利義務を引き継ぐことになります。
しかし、この相続時に株式は相続人間で準共有状態となり、権利行使者を決定しなければ議決権も行使できない状態になります。このため、単に資産を分けるという以上に、会社の経営判断に直結するという特徴があります。
また、中小企業オーナーの株式は譲渡制限が付いている場合が多く、第三者に売却して現金化することも難しいため、兄弟間で経営権を巡る紛争の火種になりやすいのです。
兄弟で株式を分け合うと意思決定が止まりやすい
株式が兄弟に分かれると、会社運営に必要な重要事項の決議がスムーズに進まなくなるリスクがあります。
例えば、兄弟で全部の株式を半分ずつとする遺産分割をしたとします。この場合、兄弟が対立してしまうと、取締役の選任・解任、定款変更、事業承継に関する方針など株主総会の決議を要する事項について、いずれも過半数を取れず、結論が出せなくなります。銀行融資や取引先との関係も「株主が争っている会社」として不安視され、会社の信用にも影響を与えかねません。
このように株式相続は単なる財産分割の問題ではなく、会社の存続や発展に直結する重大な論点であることを理解する必要があります。
兄弟で株式を相続したときに起こりやすいトラブル
経営権をめぐる争い(代表取締役・議決権)
最も典型的なトラブルは、誰が会社を実際に経営するのかを巡る争いです。
兄が「自分が跡を継ぐべきだ」と主張し、弟も経営参加を希望するような場合、代表取締役選任をめぐって対立が生じます。議決権比率が拮抗すれば、解任・選任も行き詰まり、経営の停滞を招きます。
(兄弟のみが相続人となり株式が準共有状態になると、持分の過半数による権利行使者の指定ができず、宙ぶらりんの状態となります。)
株式を現金化したい vs 事業を続けたい
兄は会社を継ぎたいが、弟は株式を売却して現金化したいというケースも頻発します。
非公開会社の株式は市場性が低いため売却が困難で、価格算定をめぐっても争いが生じやすいのが実務上の問題です。場合によっては鑑定等が必要となることもあります。
会社の信用低下や存続リスク
株主同士の対立は社内だけでなく社外にも悪影響を及ぼします。
金融機関は株主間紛争がある会社への融資に慎重になり、取引先も安定性に疑問を抱きます。結果として会社の存続基盤そのものが揺らぐ可能性があるのです。
株式の相続・遺産分割が遺産分割調停に発展してしまったら
遺産分割調停ってなに?
相続人間で遺産分割協議がまとまらない場合、家庭裁判所に申立てを行い調停で解決を図ることになります。
裁判所の調停委員を交えて話し合いますが、法的拘束力のある合意に至らなければ審判に移行するため、実質的には半ば裁判に近い性質を持ちます。
調停での株式評価や買い取り条件が争点になる
株式(非公開株式)は不動産や預金と異なり、客観的な市場価格が存在しません。
そのため調停では、会社の資産・収益力などを基に株式評価を算定する必要があり、専門知識が不可欠です。兄弟のどちらかが買い取る場合、その価格を巡って激しい対立が生じます。
弁護士が介入することで有利に進めやすい
株式評価や買い取り条件は交渉力に大きく左右されます。
弁護士が関与することで、適切な評価方法を主張し、過大な負担を避けることが可能です。調停や審判の手続に精通した弁護士が代理人として交渉に臨むことで、ご相談者様にとって有利な結果を導きやすくなります。


紛争を避ける・有利に進めるために取れる対策
遺言や事業承継計画で株式の集中承継を図る
被相続人があらかじめ遺言を作成し、経営を任せたい相続人へ株式を集中させる方法は有効です。
遺留分に配慮しつつ、公正証書遺言を用いれば紛争リスクを大きく減らせます。
株式の買い取り・売却スキームを検討する
相続発生後に紛争を避けるためには、一方が他方の株式を適切な価格で買い取る仕組みを整えることが重要です。
株式評価のルールや資金調達方法をあらかじめ計画しておくことで、後の争いを最小化できます。
感情的に判断せず弁護士に相談する
兄弟間の感情的対立を放置すれば紛争は泥沼化してしまう可能性が高まります。
法的な枠組みと客観的な評価に基づいて話を進めるためには、弁護士など専門家の助言が欠かせません。
株式の相続・遺産分割を弁護士に相談すべき理由
交渉・調停で不利にならないための戦略立案
弁護士は裁判所実務や株式評価方法に精通しており、どのように主張すれば有利になるかを戦略的に設計できます。相手方の出方を予測し、交渉を優位に進めることが可能です。
株式評価や買い取り条件を有利に調整できる
株式の価格は算定方法によって大きく変わります。弁護士が関与することで、過小評価による不利益や過大評価による過重負担を回避できます。
他士業との連携で税務・登記まで一括対応できる
株式相続は税務・登記・経営実務が複雑に絡み合います。弁護士は税理士・司法書士と連携し、相続税申告や登記手続を含めて包括的に対応できるため、ご相談者様にとって効率的かつ有利な解決につながります。
株式の相続・遺産分割は西村綜合法律事務所へご相談ください
会社の株式が相続財産に含まれる場合、兄弟間での争いは避けて通れないことが多くあります。
経営権や株式評価をめぐる問題は高度に専門的であり、ご相談者様自身の判断だけで進めると不利益を被る危険性があります。当事務所は地元岡山に密着し、初回相談は無料で受け付けています。オンライン面談にも対応しており、遠方やご多忙の方もご利用いただけます。
経験豊富な弁護士が迅速に対応し、ご相談者様にとって有利な解決へ導きます。まずはお気軽にご相談ください。