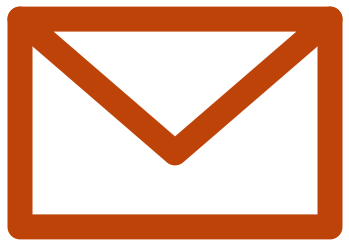相続手続きを兄弟に勝手に進められた時の対処法と注意点
相続手続きは、相続人全員が関与して進めるべきものですが、現実には「兄弟のうち一人だけが手続きを進めていた」「知らない間に名義が変わっていた」といったトラブルが後を絶ちません。
本記事では、相続手続きを他の相続人に勝手に進められてしまった場合に、ご相談者様がどのように対処すべきか、法的な観点から解説します。


目次
勝手に相続手続きが進められてしまうケースの代表例
不動産の名義変更が勝手に済まされていた
不動産の名義変更には、本来であれば相続人全員の合意を得たうえで遺産分割協議を行い、必要な書類を揃えて法務局で手続きをする必要があります。
しかし、現実には一部の相続人が他の相続人の同意を得ないまま、勝手に登記手続きを進めてしまう事例も存在します。特に、被相続人の生前から当該不動産に住んでいた相続人が「自分のものだ」と思い込んで単独で動くケースでは要注意です。
また、仮に名義変更が行われていたとしても、法的には遺産分割が未了であれば無効だと主張することが可能です。
預貯金が勝手に解約・引き出されていた
相続発生後、被相続人名義の預貯金を勝手に解約・引き出す行為は、他の相続人の権利を侵害する不正行為に該当する可能性があります。
そのため、早期に残高証明や取引履歴の開示を求めることが重要です。解約や引き出しが発覚した場合、その資金の使用目的等を確認し、必要であれば返還請求や不当利得返還請求を行うことも視野に入れましょう。
遺産分割協議書が勝手に作成・送付されてきた
被相続人の葬儀や四十九日法要が終わったあとに「こう決まりましたので署名・押印してください」と、一方的に遺産分割協議書が送付されてくるケースは多々見受けられます。
このような書類が送られてきた場合、内容を十分に確認せずに応じてしまうと、後から取り返しのつかない事態となるおそれがあります。遺産分割協議書は相続人全員が内容に合意し、押印することで初めて法的効力が生じるものです。記載された財産が全てなのか、自分の取り分が正しく反映されているかを慎重に検討すべきです。
遺言書を見せてもらえず、内容が不明なままだった
遺言書が存在することは聞いているものの、その内容を見せてもらえない、あるいは存在自体を曖昧にされているという相談も少なくありません。
遺言書が存在するかどうかは、公正証書遺言であれば公証役場で確認できますし、自筆証書遺言であれば家庭裁判所の検認手続きを通じて開示が求められます。遺言の有無や内容を隠されたまま手続きが進められることは、他の相続人の権利を著しく侵害する行為であり、正当な手続きとは言えません。
相続手続き・遺産分割における法的な注意点
遺産分割協議には相続人全員の合意が必要です
民法上、遺産分割協議は相続人全員の合意があってはじめて成立します。
したがって、手続きに関与していない相続人がいるにもかかわらず、勝手に遺産分割協議が進められている場合、その効力を争う余地は十分にあります。協議に合意していない旨を明確にすることが、まず必要な一歩です。
預貯金の引き出しや名義変更に必要な書類を確認しましょう
預貯金の解約や名義変更に際しては、通常、相続人全員の印鑑証明書や署名入りの同意書が求められます。
ただし、一部金融機関では独自の判断で払い戻しに応じることもあると言われています。実務上の運用と法的な原則には差がある点に注意が必要ですので、ご相談者様自身の実印や印鑑証明が無断で使われていないか、改めて確認し不審な点があれば弁護士に相談するべきです。
遺産分割が勝手に進められていた際にまずやるべきこと
まずは事実関係を正確に把握することが重要です
相続手続きに関して不審な動きがあった場合、感情的に問い詰めたりせずにまずは客観的な事実を集めることが最優先です。
財産の全体像、手続きの進捗状況、書類の有無などを把握することで、自分の権利がどこまで侵害されているのかが明確になります。情報の取得と同時に、相続人間のやり取りは文書で残しておくことが望ましく、後の証拠保全にもつながります。
金融機関や法務局に情報照会を行う方法
被相続人の口座情報や不動産の登記事項証明書は、相続人であれば取得することが可能です。
たとえば、預貯金の残高証明や取引履歴、不動産の登記事項証明書を取得すれば、名義変更の有無や、誰がどのように関与していたかが明らかになります。これらの手続きは弁護士を通じてスムーズに行うこともでき、不正が疑われる場合には早期対応が可能になります。
兄弟に内容の開示を求め、交渉する際の注意点
相手方が親族であっても、法的な交渉と同様の慎重さが求められます。感情的に詰め寄るのではなく、内容の開示を文書で求め、必要に応じて録音や記録を残しましょう。
交渉が進まない場合や、逆に威圧的な対応を受けた場合には、弁護士を通じた代理交渉に切り替えるべきです。無理な話し合いを避け、法的な枠組みの中でご相談者様にとって有利な解決を目指すべきです。
不正が明らかであれば、無効主張や損害賠償請求も可能
仮に他の相続人が遺産分割協議書を偽造して提出していた場合や、印鑑を無断使用していた場合は、協議の無効主張や、損害賠償請求が可能です。
これらの行為は、場合によっては刑事責任(私文書偽造・有印私文書偽造)にも問われます。法的手続きに進む場合は、証拠の確保と弁護士による判断が非常に重要です。


遺産分割協議が難航・決裂したらどうなる?
家庭裁判所での遺産分割調停を申し立てる
遺産分割協議が成立しない場合は、家庭裁判所に対して遺産分割調停を申し立てることができます。
調停では、裁判所が選任した中立の調停委員が関与し、相続人同士の話し合いを取りまとめます。感情的な対立がある場合でも、第三者の調整によって冷静な対話が促されるため、ご相談者様にとって有利な形での合意を目指すことが可能となります。
調停でも解決しない場合は審判に移行します
調停で合意に至らなかった場合、手続きは審判へと移行します。
審判では、裁判官が法令と証拠に基づいて遺産の分割方法を判断し、各相続人の取り分を決定します。審判は法的拘束力を持つため、その内容に従って手続きを進めることになります。審判に備えては、事前に弁護士とともに主張や証拠の整理を行い、戦略的に準備を整えることが重要です。
預金の使い込みが疑われる場合の民事・刑事対応
相続開始前後に被相続人の預金が特定の相続人により不正に引き出されていた場合には、民事上の不当利得返還請求や損害賠償請求が可能です。
さらに、その行為が故意で違法性が高いと判断される場合には、刑事告訴(横領罪など)の検討も視野に入ります。ただし、刑事手続に進むためには客観的かつ十分な証拠が必要となるため、事前の証拠収集と法的な判断が極めて重要です。民事請求と並行して進めることで、金銭的な回収を図る現実的な手段となります。
兄弟との相続トラブルで弁護士に相談すべきタイミング
自分だけ情報が得られない状態が続いている
相続に関する財産の内容や手続きの進行状況について、自分だけに情報が提供されていない場合、他の相続人による不当な取り扱いを受けている可能性があります。情報の共有が不十分なままでは、ご相談者様が本来取得できるべき相続分を適切に主張・確保することが難しくなります。情報格差は不利な結果に直結するため、早期に弁護士へご相談いただくことが重要です。
勝手に手続きされて事後報告だけ受けた
「手続きはすでに終わった」と事後的に一方的な連絡を受けた場合でも、その手続きが法的に有効であるとは限りません。
相続人全員の合意がないまま進められた遺産分割や名義変更等は、無効を主張できる余地があります。押印・同意をしていないにもかかわらず手続きが完了しているような場合は、法的観点から正当性を確認し、必要に応じて是正措置を取る必要があります。
通帳・遺産の一部が見つからない・説明されない
相続財産の全容が不明確なまま協議を進めることは、ご相談者様にとって明らかに不利です。
被相続人名義の通帳、有価証券、不動産登記簿などが提示されない、または所在について説明がされない場合、財産の隠匿や使い込みの可能性も否定できません。そのような状況では、弁護士を通じて財産調査や情報開示請求を行うことが、有効かつ実効的な手段となります。
精神的に強く出られず、不利な内容で押し切られそうなとき
相続人間の力関係や、家族関係における心理的な影響によって、自己の権利を十分に主張できず、不利な条件での合意を迫られることがあります。
このような状況では、弁護士が代理人として交渉を行うことで、ご相談者様の立場を法的に守ることが可能です。相手との直接交渉を避け、冷静かつ適正な条件で手続きを進めるためにも、早期の相談が推奨されます。
相続のご相談は西村綜合法律事務所へ
相続をめぐる兄弟間のトラブルは、感情と利害が複雑に絡み合う難しい問題です。
西村綜合法律事務所では、岡山に密着した法律サービスを提供し、初回相談を無料で承っております。オンライン面談も可能ですので、遠方にお住まいの方や多忙な方も安心してご利用いただけます。経験豊富な弁護士が迅速かつ的確に対応いたしますので、「勝手に相続を進められてしまった」とお感じの方は、ぜひお早めにご相談ください。