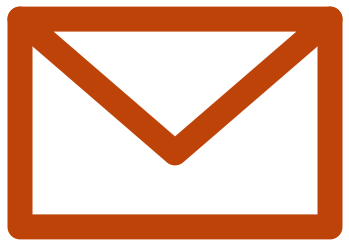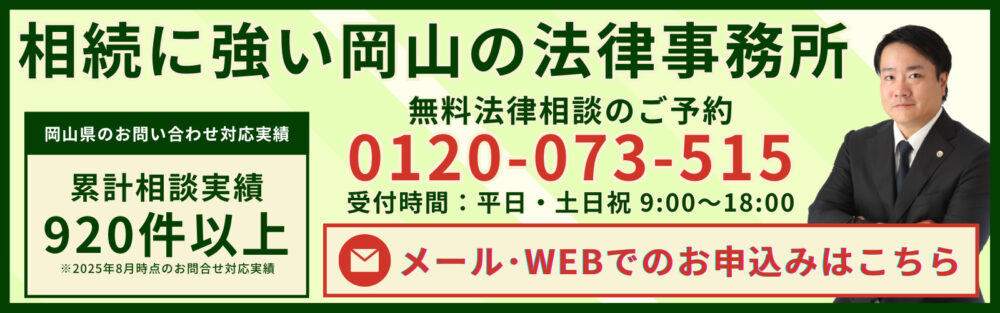遺産隠しや使い込みに対する不当利得返還請求って?遺産相続に強い法律事務所が解説
遺産の使い込みは訴訟に発展することも少なくない問題です。それだけでなく、使い込まれた遺産は返還請求をしなければ戻って来ません。今回は、”遺産の使い込み”への対抗手段である不当利得返還請求について詳しく解説いたします。
目次
不当利得返還請求って?
不当利得返還請求とは、相手方が法的な根拠なく得た利益を返還するよう求める法的手続きです。
相手が得た利益が不当利得として成立するためには、下記の4つを満たしている必要があります。
- 他人の財産や労務から利益を得た
- 他人に損失を及ぼした
- 利益の獲得と他者への損失が因果関係で結ばれている
- 利益の獲得に法的な原因がない
上記のように、一方が何らかの理由で他者から財産を受け取ったり使い込んだりし、その結果として他者が損害を受けた状態を指します。
返還を求める際は、その利得が不当であるという事実を明らかにしなければなりません。
不当利得として返してもらえる範囲
原則としては”現存利益”が上限
利益が現在も存在し、価値として残っている部分についてのみ、返還を求めることができます。これが「現存利益」と呼ばれるものです。
例えば、ある相続人が故人の貯金を勝手に自己の銀行口座へと移したとします。その貯金がまだ手つかずで口座に残っている場合、移した全額が返還請求できる不当利得として扱われます。
しかし、その相続人が貯金をすべて散財してしまい、何も残っていない場合は、”現存利益”は無いとされてしまうため返還を求めることは基本的にできません。
不当利得の自覚があった場合は利息つきで賠償となる
もし相手方が不当に利益を得ていることを自覚していた場合、これは法的に「悪意があった」とされる状態です。
相手方が不当利益を得ていると認識していた場合、現存する利益に留まらず、得た利益全体について法律に基づく年3%の利率で計算された利息を加えた総額を返却する責任があります(民法第704条による)。
これにより、時間が経過したことによる損失もカバーできる場合があります。そのため、「相手に悪意があったかどうか」は不当利得返還請求を行う上で非常に重要な項目です。
不当利得返還請求の時効
不当利得返還請求には時効が存在します。
2020年4月1日以降に発生した不当利得返還請求権は、権利を行使できることを知ったときから5年間、権利を行使できるときから10年間です。
一方、2020年3月31日以前に発生した不当利得返還請求権は、権利を行使できるときから10年間で、主観で変わる5年間の消滅時効期間は適用されません。
相続における不当利得の例
相続においては、以下のような行為が不当利得になる可能性があります。
故人の預貯金を使い込んでいた
故人の預貯金を無断で引き出し、個人的な支出に利用していた場合、これは不当利得にあたります。
故人の資産を勝手に売却した
相続人が故人の不動産や貴重品を勝手に売却し、その売却益を私的に利用した場合も不当利得となりえます。
株式配当や賃料等を勝手に受け取っていた
故人名義の株式からの配当や賃貸物件の賃料を、故人の死後に勝手に受け取っていた行為も、不当利得に該当します。
また、上記以外にも「生命保険の勝手な解約」や「株式の勝手な売却」も不当利得に該当します。細かい事例については弁護士に相談し、ご自身が損することのないような対応を心がけましょう。
不当利得返還請求のポイント
不当利得の証拠を集めましょう
不当利得返還請求を成功させるためには、適切な証拠の収集が必要不可欠です。
使い込みや資産の不正な売却を示す銀行口座の取引明細書、不動産売買の契約書、収益の領収書など、どの時点でどの程度の資金が使用されたか、当該者がその行為に自覚があったかどうかを証明する資料(例えば録音ファイルやメッセージのやりとりなど)が必要です。
遺産の保全処分を検討する
不当利得を享受している者が経済的な余裕がなく、遺産をさらに使い込む可能性がある場合は、裁判所に保全処分を申し立てることが重要です。
家事事件手続法における「保全処分」とは?
調停や審判を申し立てられた際、家庭裁判所は状況に応じて仮の差し押さえや仮の処分、あるいは財産管理人の指名など、適宜の措置を講じることがあります。これらの措置は、資産の権利変更や消失を未然に防ぐためのものです。これを特に「調停前の処分」(第266条1項)や「遺産分割審判前の保全処分」(第105条1項)と称します。
不当利得返還請求は弁護士への依頼をおすすめします
複雑な証拠収集や保全処分の申立ては専門的な知識が必要です。これらの手続きは弁護士に依頼することで、スムーズかつ適切に行うことができます。
例えば証拠集めの段階では、故人の銀行口座取引から資金の動きを確認することができます。しかし、その取引が相手方によるもなのかどうかは分かりません。相手方の取引記録も取得できれば良いですが、不当利得の自覚がある場合は相手はなかなか応じてくれないでしょう。しかし弁護士であれば開示請求を行うなどの対応が可能ですので、証拠集めがスムーズに進みます。
保全処分については、不当利得返還を求め側が、経緯を詳細に記載した申立書を裁判所に提出する義務があります。これも個人で準備するには難易度が高いため、相続問題に精通した弁護士のサポートを受けることをお勧めいたします。
不当利得返還請求をお考えの方は弁護士へご相談ください
不当利得返還請求には多くの複雑な手続きが伴いますので、ぜひ私たちにお任せください。当事務所では岡山にお住まいの方や「岡山での相続を関東で進めたい」といった方向けに無料相談を実施中です。ご都合に合わせてご相談いただけます。