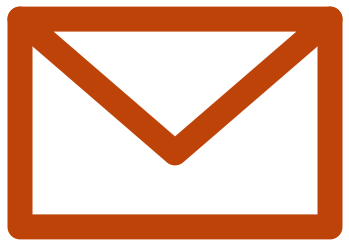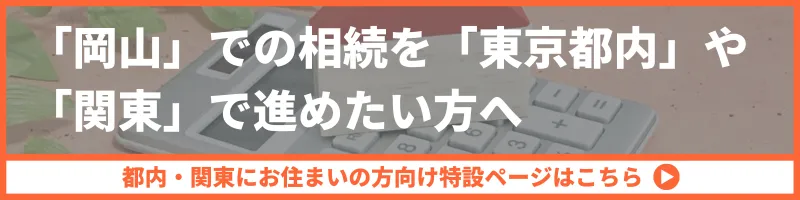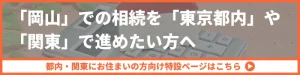相続の範囲や流れって?遺産相続の基礎知識とポイントを弁護士が解説


遺産相続とは、相続人(財産を受け取る人)が、被相続人(亡くなった人)が残した権利、財産、義務を引き継ぐことを言います。
人が死亡した場合、その亡くなられた方と一定の関係にある方は、遺産相続の問題に直面することが多々あります。本稿では、遺産相続に関するごく基礎的な知識についてお話致します。現在、遺産相続の問題を抱えている方や、今後遺産相続の問題が発生した場合にどうすべきか悩んでいる方には是非目を通していただければと思います。


目次
1 相続人となることができるのは誰か?
誰が相続人となれるのかということですが、相続人の範囲や順位は法律で定められており、被相続人死亡時の状況(配偶者や子の有無等)によって異なります。
(1) 被相続人の配偶者と子ども
被相続人に配偶者がいる場合は、配偶者が常に相続人になります。
被相続人と配偶者との間に子どもがいれば、子どもも相続人になります。なお、その子どもが被相続人と血のつながりがない場合でも、養子縁組により被相続人と法律上の親子関係がある場合は、相続人となります。
(2) 被相続人の両親
被相続人が独身で子どももいない場合は、第2順位の親が相続人となります。
両親が死亡している場合は、祖父母が相続人になります。また、被相続人に配偶者はいるが子どもはいないという場合、配偶者と被相続人の両親が相続人となります。
(3) 被相続人の兄弟姉妹
被相続人が独身で子どももなく、両親も祖父母も死亡している場合は、被相続人の兄弟姉妹が相続人となります。
(4) 法定相続人以外の人に財産を残したい場合
法定相続人以外の人に財産を残したい場合には、遺言書を書いて第三者へ遺贈する必要があります。
遺贈とは、遺言で財産の全部又は一部を、相続人又は相続人以外の人に無償で贈与することをいい、遺言の効力は、遺言者が死亡した時に発生します。遺言の内容は、遺言者の意思により、自由に決めることができます。
2 相続財産の範囲と遺産分割の対象となる財産の範囲


では、相続財産と言っても、どこまでが財産と言えるのでしょうか。また、遺産分割される財産はどこまでが対象になるのでしょうか。
(1) 相続財産の範囲
相続人が確定したとして、ではどのようなものが相続の対象になるのでしょうか。
相続が開始すると、被相続人の財産に属した一切の権利義務は、原則として相続人がすべて承継することになります。一切の権利義務とは、被相続人が所有していた財産的価値のある資産や負債、権利義務関係などです。
例えば、現金や預貯金、不動産や株券などの有価証券、投資信託、各種の積立金やゴルフ会員権などがあります。逆に被相続人が借金をしていた場合には借金も相続の対象になりますし、買掛金などの債務を負っていた場合にはその債務も相続の対象になります。
反対に、相続財産にならないものもあります。まず、一身専属的なものは相続財産になりません。例えば被相続人が生前、会社勤めをしていたとして(つまり、雇用契約上の地位を有していたとして)、相続人がその雇用契約上の地位を承継することはありません。
また、墓地や墓石、仏具、神具などの祭祀関係の財産も相続財産には含まれません。財産分与請求権や生活保護法に基づく保護受給権についても一審専属的なものであるため相続できませんが、例外的に、一定額の給付を請求できる権利として具体化していた場合(例えば、財産分与について一定の給付を定める調停が成立している場合など)は相続可能となることもあります。保証債務については、保証債務によって相続性が認められるかが異なり、身元保証は相続性を否定、通常の保証は相続性を肯定するというのが一般的な考え方です。
(2) 遺産分割の対象となる財産の範囲
上記(1)では、相続財産の範囲を述べましたが、相続の対象となる遺産がすべて遺産分割の対象となるわけではありません。
遺産分割の性格や機能等から、遺産のうち遺産分割の対象から除かれるものがあります。例えば、現金などの可分債権(普通預金債権、通常貯金債権及び定期貯金債権は遺産分割の対象となるのが判例です)や金銭債務は、遺産分割協議を待つまでもなく相続開始により当然に分割されることになります。このように、遺産の範囲と遺産分割の対象となる財産の範囲は一致しません。
3 遺産相続の方法
法は、相続するか否かについて相続人に選択の自由を認めています。すなわち、相続人に一定の期間(これを「熟慮期間」と言います)を区切り、相続財産を負債含めて全面的に承継するのか、逆に財産の承継を全面的に拒否するのか、相続した資産の範囲内で債務などの責任を負うのか、いずれかを選択できるようにしています。
それぞれの対応方法によって効果が全く異なってきますし、期間制限がある対応方法もあるので、相続が起こったときにはどの対応をとるか、しっかり検討することが大切です。そこで、以下ではこの3種類の相続への対応方法について、個別に解説します。
(1) 単純承認
単純承認とは、相続に限定をつけず、権利も義務もすべて承継する相続方法です。単純承認するときには、被相続人のプラスの資産も承継しますが、マイナス資産(負債)も承継します。通常のケースでは、相続人全員が単純承認をして、そのまま相続人同士が集まって遺産分割協議をすることが多いです。
ただ、上記のとおりマイナス資産も承継するため、被相続人が借金をしていた場合に単純承認してしまうと、相続人は被相続人の代わりに借金返済をしなければならないので、注意が必要です。単純承認してプラスの資産を取得したものの、承継した負債が大きく、結局プラスの資産でも負債を賄いきれないという事態にならないようにしましょう。
(2) 相続放棄
相続への対応方法の2つ目は、相続放棄です。相続放棄とは、相続開始による包括承継(被相続人の一切の権利義務を承継すること)の効果を全面的に拒否することを言います。
この場合、プラスの資産もマイナスの負債も相続することがないので、被相続人に借金がある場合には相続する必要がなくなり、返済の義務を負うことはありません。
ただ、相続放棄をすると、プラスの資産も相続することができなくなるので、被相続人に資産がある場合には、それも相続できなくなってしまいます。被相続人の遺産に資産と負債の両方があって、差し引きすると資産価値が負債を上回っている場合に相続放棄をすると、損をしてしまうおそれがあります。また、被相続人の遺産内容に実家の不動産などの守りたい財産がある場合、相続放棄をするとその不動産の相続をすることもできません。兄弟が単純承認をしてくれて、実家を引き継いでくれるなら不動産がなくなることはないですが、誰も相続しない場合には、最終的にその財産は国庫に帰属することとなります。
相続放棄した場合、代襲相続も生じません。つまり、被相続人の死亡時、すでにその子どもが亡くなっていた場合、その子に子どもがいれば相続が発生することになりますが、相続放棄した場合はその放棄した人を代襲することはありません。
(3) 限定承認
相続への対応方法の3つ目は、限定承認です。限定承認とは、遺産内容を調査して、プラスの資産がマイナスの負債を上回っている場合、そのプラス部分のみを相続する方法です。負債が資産を上回っている場合には相続は起こりません。
前述のように、相続放棄すると負債を相続せずに済みますが、プラスの資産まで受け取れなくなるのでプラスの資産が上回る場合に損をする可能性があります。これに対し、限定承認をすると、プラスの資産が上回る場合にはその上回ったプラス分は受け取ることができるので、そのようなリスクを避けられます。
ただし、限定承認をするためには共同相続人全員でする必要があります。相続人のうちひとりでも単純承認をしたり相続放棄をしたりすると、1人で限定承認することはできないので注意が必要です。
4 相続税について
次に、相続税について説明したいと思います。課税される額がどれくらいなのか、どのような計算式なのかを簡単に見ていきましょう。
(1) 相続税とは
相続税とは、被相続人の遺産を受け継いだ場合にかかる税金であり、「①課税対象額×②税率-③控除額」で求めることができます。
以下、1億円の相続財産があり、相続人の数は4人という設定で相続税額を計算してみましょう。
(2) ①課税対象額
課税対象額は、「相続財産の合計金額-基礎控除額」で求めることができます。相続財産の合計額を算出するにあたって、不動産を適切に評価することは重要です。
基礎控除額は、「3000万円+相続人の数×600万円」で計算されます。つまり、今回の場合だと、3000万円+4人×600万円=5400万円が基礎控除額となります。
以上より課税対象額は、1億円-5400万円=4600万円となります。
(3) ②税率
税率は、課税対象額に応じて異なります。国税庁のホームページなどに速算表が掲載されておりますので、詳しくはそちらをご覧いただきたいと思いますが、今回の場合だと税率は20%となります。
(4) ③控除額
控除額についても、②税率と同様、課税対象額によって異なりますが、今回の場合だと200万円が控除額として認められます。
(5) 相続税額
以上より、相続税は、「4600万円×20%-200万円=720万円」となります。今回のケースでは相続税が発生しましたが、基礎控除により相続税が課税されないケースはよくあります。しかし、課税されるかどうかは、相続財産の適切な評価が前提となってきますので、その点は怠らないよう注意が必要です。
5 遺産相続の流れと必要な手続き


では、遺産相続の流れはどうなるのでしょうか。競技でまとまらない場合、調停、審判、と移行していきます。
(1) 遺産分割調停
遺産分割は、基本的に当事者間の協議によって行いますが、協議がまとまらない場合は、管轄の家庭裁判所に遺産分割調停の申立てをし、調停内で話し合いを行うことになります。
調停という制度について簡単にお話しておくと、調停委員2名と裁判官1名で構成される調停委員会が、申立人(遺産分割調停を申し立てた人)と相手方(遺産分割調停を申し立てられた人)から交互に話を聞き、合意を目指す手続きとなります。公的機関が申立人と相手方の間に入ることになりますが、あくまで話し合いでの解決を目指すものに過ぎないため、遺産分割調停で合意が成立しないのであれば、次に述べる遺産分割審判に移行することになります。
もっとも、基本は遺産分割調停での合意を目指し、また仮に審判移行しても自分に有利な審判を得られるよう、調停段階あるいはそれ以前の段階からしっかりと準備しておくことが重要です。
(2) 遺産分割審判
遺産分割調停が不成立に終わると、遺産分割審判に移行します。調停が話し合いの手続きであったのに対し、審判は裁判官が職権で証拠調べや事実の調査を行い判断するものですので、調停に比べて手続きが厳格です。
6 遺産相続のポイント
以上流れをお話ししてきましたが、遺産相続においては、遺言の作成、弁護士への早期相談が大きなポイントと考えます。
(1) 遺言の作成
悲しいことに、今まで仲の良かった親族らが相続財産をめぐって骨肉の争いをすることは少なくありません。このような事態は、争いの渦中にいる相続人だけでなく、亡くなった被相続人としても不本意なものでしょう。そうした事態をなるべく防止し、被相続人の死後、相続人らに財産を有効・有意義に活用してもらうため、遺言の作成はとても重要です。
遺言を作成していない場合、相続人らは法定相続分に従って遺産分割することになります。「法律に従って分けるのだから、文句はないのでは」と思われるかもしれませんが、例えば子どもの頃から被相続人と一緒になって家業を助け、苦労や困難を共にして頑張ってきた相続人と、そうではなく家に寄りつきもしなかった相続人とで全く差を設けないのだとすれば、却って争いになり得ます。このように、自分のおかれた家族関係をよく考え、最も適切な相続の仕方を遺言できちんと決めておくことは、残された者への最大の配慮であり礼儀と言えるでしょう。
遺言には、遺言者が自ら遺言の内容の全文(目録を含むすべて)を手書きし、かつ、日付、氏名を書いて、署名・押印することにより作成する自筆証書遺言、遺言者が公証人の面前で遺言の内容を口授し、それに基づいて公証人が作成する公正証書遺言などがあります。費用はかかりますが、自筆証書遺言よりも公正証書遺言の方が確実・安全だと言えます。
(2) 弁護士への早期相談
以上のとおり、遺産相続のごく基礎的なポイントをお話致しましたが、個別具体的なケースに応じて検討すべきポイントは異なる上、複数相続人がいる場合、出来る限り皆が納得できる解決を目指すことも必要になります。
相続人間の仲が非常に良く、協議であっさりまとめることができれば問題ありませんが、多くのケースでは遺産分割方法に納得できない相続人が登場し、収拾がつかなくなります(元々は相続人間の仲が良かったが、遺産相続の問題が顕在化した途端にそれまでの関係が破綻するということもあります)。遺産相続の問題は解決までに時間がかかる上、感情的な対立も生じますから、話し合いを続けていくにつれて疲弊し、強情な相続人が自分の言い分を最後まで貫き、不公平な遺産分割が成立するということもあり得ます。そのような事態に陥らないよう、少しでも遺産相続の問題解決に不安があるのであれば、早期に弁護士に相談することをお勧め致します。
当事務所では遺産相続に関して豊富な解決実績がありますので、遺産相続にお困りの方はお気軽にご相談いただければと思います。