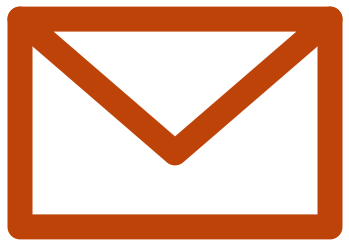相続で問題になるタンス預金の発見・遺産分割・申告のポイント
この記事では、相続において問題となりやすい「タンス預金」について、実務的な観点から詳しく解説します。
相続財産の中でも特に発見が難しく、親族間のトラブルや税務上のリスクを引き起こしやすいのが現金、いわゆるタンス預金です。
本記事では、典型的な発見パターン、隠された場合の対応策、税務申告上の注意点、さらにトラブル防止の戦略までを包括的にご紹介します。相続を有利に進めるために何をすべきか、どのタイミングで弁護士に相談すべきかの判断材料にもなります。


目次
相続で「タンス預金」が問題になるのはなぜか
遺産の中でも見落とされやすく、争いの火種になりやすい
相続財産の中でも「現金」は記録が残りにくいため、相続人によって発見の有無や扱いが変わりやすい財産です。
通帳や証券類とは異なり、明細や残高証明が存在しないため、相続人の1人が密かに持ち出しても他の相続人が把握できないことがよくあります。その結果、「現金がなかった」「いや、見た」など主張が対立し、遺産分割協議が頓挫する原因になりかねません。弁護士の立場からすると、初期の証拠保全が鍵を握ります。
見つかれば相続税・見つからなければ相続トラブル─隠れたリスクが大きい
現金が発見された場合は相続税の課税対象となる一方、見つけられなければ、実際に存在していたかどうかを巡って親族間で疑念が深まり、関係悪化や紛争の原因になります。
つまり、タンス預金は「見つかっても大変、見つからなくても大変」という厄介な遺産です。特に他の相続人に隠匿された場合には、不当利得返還請求などの法的対応を検討せざるを得ません。
「うちにもあったかも…」タンス預金が疑われる典型的な状況
銀行口座に不自然な出金履歴がある
被相続人の通帳を確認した際、定期的な出金や大きな金額の引き出しが続いているにも関わらず、何に使われたかが不明な場合には、タンス預金化されていた可能性があります。
特に高齢者の単身世帯では、「通帳は信用できないから現金で管理する」として自宅に保管するケースが少なくありません。遺族は通帳履歴と合わせて、出金時期・金額・回数を客観的に検討する必要があります。
遺品整理中に多額の現金・封筒・金庫が出てきた
遺品整理の際、引き出しやタンス、冷蔵庫の中から現金入りの封筒や鍵付き金庫が出てくる事例は実際に多く存在します。
額面が大きい場合、それが被相続人の資産なのか、特定の相続人が準備していたのか、証拠に基づいて判断する必要があります。特に金庫については、誰が鍵を管理していたかが後々の法的主張の根拠になります。
同居親族がやけに金銭事情に詳しい
被相続人と同居していた親族が、現金の管理状況や「どこに何があったか」を過剰に把握している場合、それはタンス預金の存在を知っていた、あるいは関与していた可能性があります。
事後的に「預かっていただけ」と主張されることもありますが、法的にはそれが遺産にあたるかどうかの立証が重要となります。
生前の言動に違和感があった場合のチェックポイント
「家に現金があるから安心」と言っていた
生前の口癖や発言から、被相続人がタンス預金を好んでいたかどうかを推測することも可能です。
「銀行は信用ならん」「現金で持っておくのが一番」などの言動は、タンス預金の存在を裏付ける証拠の一つになります。
通帳やカードの扱いが異常に慎重だった
通帳を隠していた、カードの暗証番号を誰にも教えなかった、などの行動も要注意です。
こうしたケースでは、現金主義で日頃から自宅に多額の現金を保管していた可能性が高くなります。
タンス預金はどのように把握するべきか?
まずは遺品整理・通帳確認から着手
タンス預金の有無を把握するためには、まず遺品整理や預貯金口座の明細確認から始めるのが基本です。
自宅内をくまなく確認し、現金・封筒・金庫・貸金庫などを調べるとともに、通帳やATMの出金履歴を照合することで、不審な現金の動きがないかを探ります。
金庫がある場合は、鍵や暗証番号の取得・開錠手続きも必要です。こうした作業は、後のトラブルを避けるために相続人全員の立ち会いや、写真・動画などによる記録を残しながら進めることが望ましいです。
他の相続人に隠されている場合の対処法
家庭裁判所を使って追及・確認を求める
タンス預金の存在が疑われ、特定の相続人が管理・隠匿している可能性がある場合は、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることが有効です。
その中で、相手方に対して「生前に多額の現金を管理していた形跡がある」「遺品整理時に現金が見つかったが、開示されていない」などの主張を行い、財産の内容について協議・確認を求めることができます。
家裁の調停で追及できる範囲と限界
ただし、家庭裁判所の調停はあくまで任意の話し合いであり、相手方に対して強制的にタンス預金の開示や提出を命じる権限はありません。
相手が事実を否認し、証拠が乏しい場合には、調停が不成立となる可能性があります。その場合は審判または民事訴訟に移行し、証拠に基づいて裁判所の判断を求める必要があります。したがって、早期の段階で証拠保全を行うことが極めて重要です。
弁護士に依頼して調べられるのか?
弁護士は、銀行口座や金融資産の法的照会を行うことは可能ですが、個人宅内の現金の有無や所在を直接調査する権限はありません。
ただし、弁護士は次のような間接的手段を駆使して、タンス預金の存在を推認し、法的主張を構築することができます。
- 通帳の出金履歴や振込記録から、現金の流れを把握
- 相続人間の証言・生前の発言内容などから状況証拠を整理
- 遺産分割協議書や調停の中で、現金の所在に関する説明責任を追及
最終的には、調停・審判・訴訟といった法的手続きの中で、主張と証拠をもとにタンス預金の存在を明らかにしていく必要があります。そのためにも、法的知識と交渉力を持った弁護士のサポートを早期に得ておくことが、ご相談者様にとって有利な展開につながります。
見つかったタンス預金の相続上の扱いとは?
原則は「現金=遺産分割の対象」
タンス預金は、被相続人の所有していた財産である限り、他の金融資産と同様に遺産分割の対象となります。
発見された現金が被相続人のものであると確認された場合、たとえ特定の相続人が管理していたとしても、その人の単独財産にはならず、相続分に応じた分配が求められます。
他の相続人が独占していた場合の法的手段
不当利得返還請求とは?
相続人の一人がタンス預金を独断で保持・使用していた場合、民法703条以下の不当利得返還請求が可能です。
加えて、使用状況や隠匿行為の有無によっては、709条の不法行為に基づく損害賠償請求も検討されます。請求の根拠は状況により異なるため、弁護士に 相談しながら慎重に進めましょう。
使い込みがあった場合の民事・刑事対応
使い込みが あまりにも悪質な場合、刑法上の横領罪が成立する可能性もあります。
ただし、相続人間の財産関係は複雑で、「他人の財物」と評価しづらい場合もあるため、刑事告訴が認められるかはケースバイケースです。実務では、感情的な対立を避け、民事的な交渉や調停によって解決を図ることが一般的です。
タンス預金も相続税の対象になる
相続税法では、被相続人の死亡時に存在した現金等は全て課税対象です。タンス預金も例外ではなく、相続税の申告が必要です。
これを怠ると、後に税務調査で発覚し、多額の追徴課税や加算税のリスクを伴います。現金を発見した段階で、速やかに税理士や弁護士に相談することが、安全で有利な手続きに繋がります。


タンス預金をめぐるよくあるトラブル事例
兄弟間で「現金はなかった」と主張が対立
相続において特に多いのが、「現金の有無」に関する相続人間の食い違いです。
たとえば、被相続人と同居していた相続人が「現金なんてなかった」と言い張り、他の相続人が「生前、父(または母)が“現金は金庫に入れてある”と話していた」と反論するようなケースです。金庫があったものの空だった、タンスや仏壇の中身が整理された形跡がある、といった状況があっても、明確な証拠がない限り、法的に主張を裏付けることは困難になります。
こうした状況が続くと、相続手続きは膠着し、兄弟姉妹間の関係も悪化しやすくなります。現金の所在をめぐる「言った・言わない」の応酬は、予想以上に深刻な対立の火種になるのです。
発見した現金を独断で使い込み、後に請求されるケース
タンス預金が発見された場合にありがちなのが、「親の世話をしていたのだから」「葬儀費用に充てたかったから」といった理由で、相続人が他の相続人に無断で現金を使ってしまうケースです。
相手に悪意がなかったとしても、遺産分割協議が整う前に個人の判断で財産を処分した場合、後から「不当利得」や「損害賠償」の形で返還請求を受けるリスクがあります。特に「費用を立て替えたつもりだった」「共有財産という意識がなかった」といった説明は、法的には通用しづらい場面も多く見られます。
現金を扱う際は、金額の多寡にかかわらず、相続人間で確認を取り合う姿勢が必要です。
申告漏れを指摘され、多額の追徴課税を受けるケース
タンス預金の存在を申告しなかったことで、後日税務調査により追徴課税を受けるケースも後を絶ちません。
よくあるのは、「家の中にあった現金は自分のものと思い込んでいた」「そもそも課税対象になるとは知らなかった」といった誤解により、相続財産に含めずに処理してしまうパターンです。しかし、税務署は過去の預金引き出し履歴や、相続開始前後の現金の流れなどから調査を行い、申告漏れがあれば厳しく追及してきます。
結果として、重加算税や延滞税を含めた多額の納税義務が発生することもあり、「申告しなかった方が損だった」となるのです。
トラブルを防ぎ、円満な相続に導くための具体的戦略
早めに弁護士に相談し「証拠の確保と主張の準備」を
タンス預金は証拠が残りにくいため、初動が極めて重要です。早期に弁護士へ相談し、現金の所在や管理経緯について事実関係を整理することで、後々の主張が通りやすくなります。
遺品整理は家族だけで済ませず第三者を立てる
トラブル防止の観点から、相続人以外の第三者(専門業者等)を交えた遺品整理が望まれます。証拠保全にもなり、他の相続人への説明責任も果たしやすくなります。
遺産分割協議書に「現金の存在」も明記すること
協議書には、タンス預金を含めた現金の扱いを明記しておくことが肝要です。金額・配分を記録することで、将来の紛争を予防できます。
疑わしい場合は弁護士の依頼を躊躇してはいけません!
「怪しいけれど決定的証拠がない」と感じた段階でも、弁護士に相談することで今後の対応を設計できます。少額でも感情的トラブルに発展する前に、予防的な一手を打つことが重要です。
まとめ:タンス預金問題を放置しないことが「最も得をする」
遺産分割、相続税、人間関係、すべてのリスクを抑えましょう
タンス預金の存在を曖昧にしたままでは、あらゆるリスクが拡大します。相続分の不公平感、課税上の罰則、親族関係の悪化といった問題を未然に防ぐためには、早期対応が必須です。最初の段階で何をするか、誰に相談するかがその後の展開を左右します。証拠の確保、交渉準備、遺産分割の設計など、すべては初動の質によって変わります。
不明点があれば初回無料相談をご活用くださいタンス預金をめぐる問題は非常に複雑で、個別事情によって対応が変わります。当事務所では地元岡山で多数の相続案件を取り扱っており、初回無料相談・オンライン面談にも対応しています。お一人で抱え込まず、お気軽にご相談ください。経験豊富な弁護士が迅速に対応いたします。